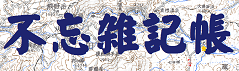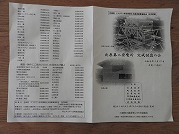|
遠刈田からあけら山の旧登山道 2019年5月30日遠刈田からあけら山に行く、旧登山道の入口まで行ってみました。 青麻山林道の横柴線の東の沢を越えたところに、「作業道」と書かれた看板がその入り口です。4輪駆動車なら何とか通れる幅の作業道で、その入り口から登ります。途中分かれ道が2回出てきますが、地検図の葉選が走っている方へ進むと、700mくらい進んだところから、山道の跡があります。草が生えていて、わずかに道だと分かります。少し進むと、大きな倒木に阻まれてしまい、これより先に進むのはやめました。作業道も、一部崩れているところがありました。 しばらく人の通ったことのないような道でした。
千年杉と白龍滝 2019年5月28日かよう会の皆さんと、千年杉・白龍滝コースを回ってきました。えぼしスキー場が水仙まつりのため入場料が必要、ということなので、少し下の前烏帽子登山道入り口駐車場に車を置いてスタート。 20分ほど歩いて千年杉コース入口へ。しばらく登ると、アサギマダラが飛んできました。ヨツバヒヨドリはまだ先なのですが、何を食べているのでしょうか。 いろいろな花が現れます。チゴユリ・ツマトリソウ・ユキザサ・・・。千年杉の近くから、シロヤシオツツジが。多い年に比べて花が少ない気がしますが、ムラサキヤシオツツジとともに咲いています。パラパラ雨が降っているようですが、林の中なので影響ありません。 石子ゲレンデに着いて、展望テラスで昼食。周りのロックガーデンにはいろいろな花が咲いています。オダマキやコマクサもありました。また、ゲレンデ内には、チングルマとコイワカガミがありました。スイセンはほぼ終わりです。ぼんやりとしていますが、展望はあります。 昼食後、石子遊歩道を白龍滝へむけて下ります。こちらの方が、北斜面なので、花が遅く、まだ花の盛りでした。下ると、ヤマツツジも現れます。白龍の滝は、緑が濃くなり見えにくくなっていました。オオルリコースを経てスキー場駐車場。車道をしばらく降りて、車のところに戻りました。 そのあと、青麻山パラコースの登山道整備へ。2台の刈り払い機で入口あたりの草むらを1時間かけてきれいにしました。
登山道整備 ろうづめ平から後烏帽子岳 2019年5月27日宮後蔵王ガイド協会の登山道整備に行ってきました。今日の現場は、ろうづめ平から後烏帽子岳に登る登山道でした。5月にもかかわらず全国的に高温が予想された通りになり、真夏のような日になりました。 刈り払い機を持ち聖山平からスタート。このルートは、4回の渡渉を経て目的地に至るルートです。春の雪解けで沢は増水し、渡る石が一部水面に沈んでいます。雪もところどころ残っています。風も無く暑さに慣れない体にこたえます。 2時間半で作業現場に到着。ここで笹の茂った道を2時間草刈りをし、2時間かけて戻りました。帰りは沢がさらに増水し、行きに使えた飛び石が使えなくなっていました。特に、澄川本流と井戸沢。じゃまな刈り払い機を持ち、ようやくの事で渡渉しました。 行き帰りの森には、いろいろな花がありました。ショウジョウバカマ、ムラサキヤシオツツジ、サンカヨウ、そして、股窪平の湿原にはミズバショウの花もあり、これはこれで楽しめる山行でした。また、残雪でまだら模様の屏風岳もとても珍しいものでした。
熊野岳 2019年5月26日朝のうちに、熊野岳まで行ってきました。先週から、日曜朝の「遠刈田朝市」が始まったので、それに寄ってから、エコーラインを登ります。まだ時間が早いので、車はあまりいません。それでも刈田岳の駐車場には1/4くらい埋まっていました。 高気圧に覆われ、快晴です。朝日連峰、飯豊連峰、吾妻連峰、安達太良山が見えています。馬の背を熊野岳に向かって歩きます。風がないので少し暑く感じます。御釜のふちには、まだ残雪、そして、熊野岳への道も一部雪が残っています。ミネザクラが咲き始めていました。 コマクサ群生地から避難小屋に行きました。小屋の扉が開きません。南側の冬季入口から入ることができました。ドアの取っ手が壊れています。道具がないので直せません。入口に、テープにその旨書いておきました。避難小屋に入れないのは困ったことで、非常時に大変なことになりかねません。 ここまで来ると、月山と鳥海山、栗駒山も見えてきました。熊野岳山頂で景色を楽しんだのち、下山にかかりました。駐車場に戻ると、続々と車が来ています。下り始めましたが、登ってくる車が続いています。早めでよかった。 途中、コマクサ平に寄りました。当然のことですがコマクサの花は、まだです。不帰の滝は水量も多く、少し上に小さな滝が見えました。また、この時期しか見えない滝:振子滝も2段に流れていました。
刈田岳とその周辺 2019年5月23日連休は渋滞に恐れをなして登らなかったエコーラインに行ってきました。 まずは、大黒天から刈田岳まで1時間ほど登ってきました。途中のロープは、一部壊れています。また登山道の一部は雪で覆われています。上から見るエコーラインの雪の壁が縞の沢には残っています。お釜が見えてきました。緑色をしています。ミネザクラが咲き始めています。稜線は、これから「桜の季節」です。 一時間弱で山頂に着くと、避難小屋はまだ冬モード。入口は冬用だけです。山頂からは、朝日連峰が見えています。展望は360°。30分くらいで下山し、刈田駐車場へ。ここから馬の背に行く登山道の入口は、雪に覆われています。 御田の神湿原に行ってみました。まだ花はありません。コバイケイソウが芽吹いてきました。途中、ホシガラスが姿を見せました。
あけら山 町役場の担当者と視察 2019年5月22日町役場の観光課、ジオパーク推進室の職員さんたちと、青麻山西面の登山道の視察に行きました。 当日は、設置中の道標の作業も兼ねてです。横柴登山口に設置した道標は、熊に壊されていました。 横柴登山口から登り、カタクリの丘で道標の修正。登山口の方向を変えました。そのあと、伐採現場脇を通りましたが、昨年に続き伐採作業が進み、広々とした雰囲気になっています。途中、伐採境界路から防火帯に移る途中で標石を見つけました。「補点」と書かれていますが、三角点標石にそっくりです。 登山路には、タニウツギが咲き、ツツジが満開でした。この道は、「ツツジロード」でした。展望ポイントからの蔵王の景色も、赤いヤマツツジがアクセントになっています。ヤマツツジに混じって、シロヤシオツツジも咲いていました。午後に用があり、あけら山の山頂から一足早く下山しましたが、有意義な一日でした。
川崎の水力発電 2019年5月18日おなりの川崎町で「川崎町の資源を生かす会」という団体が主催の、水車を使った、「北原第二発電所 完成披露の会」に行ってきました。 この団体は、川崎町で活動しているNPOの団体で、少し寄付をしたことがあります。8年前の大震災で7日間停電した経験を踏まえ、水車による発電所を作ったのをきっかけに、それよりも大規模な2号機を作ろうと計画し、5年の準備を経て今日の完成披露となったものだそうです。原子力や石油に頼らず地元の資源を使って電気をつくる、という、素晴らしい理念を実践しています。 本来なら、政府が行うべきことですが、それを待たず、草の根からという姿勢もすばらしい。水車小屋でついたそば粉で打ったそばもいただきました。 小規模水力発電はこれまで2回ほど見ています。一回は立山の山小屋が使っていました。もう一回はネパールのランタン谷の村にあった日本の団体が地元のために作った施設です。規模の大きさは違いますが、どちらも素晴らしいものだと感じました。 この国には、発電のための資源なら、太陽光・風力・水力・木材・地熱などいろいろとあるのですが、十分活用しきれない現実に、割り切れないものを感じます。
青葉祭りとすずめ踊り 2019年5月17日用事があり仙台に行くと、なんと青葉祭りの宵祭り。これまで、やっているのは知っていましたが、一度も見たことがありません。 一番町の通りには、山鉾が置かれていました。中央通りでは、すずめ踊りの中央通り流し。定禅寺通りでは、すずめ宵流し。勾当台公園と市役所前広場では杜の市と称した屋台が出て、にぎやかでした。
氾濫原 2019年5月14日かよう会の皆さんと、北泉ヶ岳麓の氾濫原へ、昨年に続き出かけました。遠刈田から車で1時間余りで泉ヶ岳大駐車場。平日のせいで、広い駐車場はガラガラです。ここで合流して、車2台で林道升沢線に入ります。途中から悪路、桑沼駐車場から歩き始めます。 今年は、大倉山の山頂を経由するコース。桑沼をかすめて、林道を少し歩いた登山道入口から、約100mの登りです。ひと汗かいた後、頂上の東屋で一休み。三角点はこのすぐそばです。キクザキイチゲ・ヒメイチゲはじめ花がたくさん。山頂あたりは、コブシの花が続いています。 下って、氾濫原。2回渡渉し、昼食。その後、ニリンソウの大群落の中を進みます。途中、シラネアオイの紫の花。ヤマカタバミの白い花、サンカヨウやヤマワサビも見えました。カツラの大木も若葉を出しています。 最後に、水の吸い込まれている地点で氾濫原終了。ここから、迂回しながら林道に戻ります。途中、シロヤシオツツジやチゴユリが咲いていました。 看板を整備するとかで、工事の立て札。1千1百万円だそうです。道標もクマに壊されていました。整備するのは大歓迎ですが、途中の倒木数か所も処理してほしいと思いました。
北屏風岳 2019年5月12日ガイド協会の皆さんと、北屏風岳に登りました。高気圧に覆われ快晴の一日です。 9時に刈田峠の駐車場。縦走路はまだ雪道なのですが、天気がいいので、車がたくさん来ています。夏道は通らず、刈田峠避難小屋をめざします。今日改めて気が付いたのは、この一帯のアオモリトドマツが、みな枯れていて、「死の林」となっていることです。ここは、この時期しか歩くことができないので、この景色は、他の季節に見ることができないのです。2年前はこんな風になっていなかった、とのことで、この1~2年で変わってしまったようです。先日新聞で報道されていたのですが、改めて驚きました。 前山・杉ヶ峰の東斜面をトラバースし、芝草峠に出ました。先週より雪が少なくなり、木道が一部出ていました。そこから北屏風への登り。ここは、一部夏道が出ていて、雪の踏み抜きなどに注意して歩くところです。途中から、熊野岳のとなりに、月山が見えてきました。朝日連峰や吾妻連峰も見えています。 12時5分に稜線。巨大な雪庇が広がっています。頂上で昼食。そのあと、キタゴヨウマツとハイマツの見分け方を教えてもらいました。球果に中にある種を見て、翼がなければハイマツ、長い翼があればキタゴヨウマツ、そして、短い翼やないものが混じっているのはハッコウダゴヨウマツだそうです。 その後、来た道を戻りますが、登りより大変。芝草峠に戻り、杉ヶ峰の東斜面を進みます。仙台三桜高校の山岳部の生徒たちや顧問が30人ほど来ていて、雪の上で遊んでいました。多くが女子生徒で、なかなか蔵王で見られない景色でした。 その後、枯れ木の中を、避難小屋を経て、駐車場に3時に戻りました。
近所の花・タイヤ交換 2019年5月11日家の周りにも、いろいろと花が咲き始めました。 まず、ウワミズザクラ。試験管を洗うブラシみたい、と言われている花ですが、今八分咲き。香りもしています。桜の仲間ですが、ソメイヨシノ他とは、花がずいぶん違っています。 小さな白い花を咲かせているのは、ミツバウツギ。葉っぱが三出複葉という形です。 オレンジ~赤の花は、ヤマツツジ。大きな花が印象的です。 そして、小さな白い花が集まっているのは、ヤブデマリ。オオカメノキの花に似ていますが、葉っぱが違います。 このように、家の周りでも、いくつか花が咲いています。連休明けの今日、ようやく夏タイヤに変えました。今回から、トルクレンチ、という道具が仲間入り。2時間弱で、2台分のタイヤ8本を交換しました。10月までこのタイヤで走ります。
水引入道 2019年5月9日南蔵王に、「水引入道」という変わった名前の山があります。標高1656mの山です。紅葉の素晴らしい山です。 この山の名の由来が、春にできる雪形。ちょうど今の時期にその雪形が見えています。杖をついた坊さんの姿です。この写真は、白石市の弥次郎こけし村の駐車場から撮影しました。
花の蛤山 2019年5月7日かよう会の人たちと、蛤山を訪れました。蛤山は花盛り。 大萱登山口から登り始めました。このコースは、急登コースですが、いろいろと見物が出てきます。ちょうどど登山道はヤマブキの花が満開でした。道端には、ヒトリシズカやイカリソウが花を咲かせています。トウゴクミツバツツジも満開です。 やがて、樹林帯を抜け吾妻連峰はじめ、福島県の山々が見えてきます。ここを過ぎると、三角点。今、コキンバイの花が満開です。 山頂広場で昼食。それから、最高地点を通過し下山です。不忘山の展望を過ぎて、下山路の階段は、ニリンソウの夢の小径。花の蛤山の花見頃の登山でした。
芝草平は雪の中・キジ 2019年5月6日10連休も最終日、ガイド協会のみなさんと、刈田峠から芝草平まで行きました。 今年は雪の量が多いようで、まったく地面を踏まずに歩けました。峠から、避難小屋めざして下り、前山は東斜面を巻き、杉ヶ峰の東斜面の大雪原をトラバースすると、芝草平に着きます。杉ヶ峰には、雪庇が並んでいたした。 途中から天候が悪化、雷が鳴る中を峠に引き返しました。 帰宅したら、庭にキジが現れて、何やらエサをつついてしばらくうろうろしていました。
青麻山大縦走 2019年5月5日自宅から歩きだし、青麻山を縦走し、路線バスで遠刈田に帰る、という、サポートのない、「大縦走」を天気のいい今日、やってみました。 8時半、自宅を出発。昨年完成した横芝登山口を目指して標高差180mの林道を歩きます。約1時間で登山口。ここから縦走路を進みます。途中、山菜取りの方と同行、いろいろと話を伺います。 カタクリの丘界隈では、やっとシラネアオイを見ました。同行氏によると、この辺りにはシラネアオイがいくらでもあったのですが、根こそぎ盗られたとのこと。彼は、「自分ちの庭に植えるのにはそんなにいらないんだが…」と言っていました。ビジネスなのでしょう。 遠白分岐で別れました。ここを過ぎると、急登が2度ほどあって、あけら山、最高地点です。ここから、急な坂を下り、登り返すと青麻山。5人ほど来ていました。 下別当コースの急坂を下ります。トウゴクミツバツツジが満開でしたヤマツツジも早いのは咲いています。だいぶ下ると、ヤマブキとヤマブキソウが真っ盛り。ニリンソウの群落の中にミドリニリンソウも見つけました。 下別当登山口に着き、ここからバス停まで1時間舗装道路を下ります。境松バス停まできましたが、バス時間を調べ、次の逆川まで歩きラーメンを食べて時間調節。2時過ぎに遠刈田に戻りました。ちょうどこの日は、神社のお祭りだったようで、御神輿の収納の時間だったようです。山の中まで聞こえた花火の音が祭りのおしまいの合図だったようです。 家を出て6時間、山道歩き3.5時間、林道歩き2時間、バス待ち時間0.5時間の青麻山大縦走でした。
全日本こけしコンクール 2019年5月3日子供一家を白石蔵王駅に送りに行ったついでに、ホワイトキューブで今日から行われる、全日本こけしコンクールをのぞいてきました。 広い体育館に、いろいろなイベントが行われています。最大のものは、なんといってもコンクール。第1部の伝統こけしから、第4部の新作こけしまで、たくさん出品された中で、賞が決まったようです。内閣総理大臣賞は、肘折のこけしでした。 各系統の工人さんの即売がありました。これまで我が家のコレクションになかった、津軽系のこけしを一つ購入しました。小島利夏工人のこけしで、とっても優しい目をしています。アイヌ模様や、大きな花を描いた、津軽系独特のこけしです。髪の毛はふさふさ。くびれた胴の黄色が鮮やかです。
五月になって、花いろいろ 2019年5月2日今年は、なんと10連休。遠刈田の町もにぎわっています。道路も渋滞。 ここまで来ると、花もいろいろ。山桜が青空に映えています。ウワミズザクラは、もう少し。スミレは満開。ツツジはもう少し。ブルーべリーも花盛り、ただし、ヒヨドリが花を食べてしまうので、ネットをかけています。
このページのトップへ 前月の記事へ
(C)Akihiko URAKAWA
|