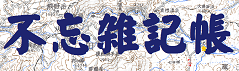|
新雪の刈田岳 2018年11月27日麓から見ると、蔵王連峰の稜線は、白く雪を被っています。好天が続く本日、かよう会の皆さんと刈田岳に登ってきました。 8時40分過ぎ、すみかわスノーパークを出発、蔵王古道経由です。蔵王古道にも雪はありますが、まだ十分歩ける状態です。40分で賽の磧。さらに1時間20分で大黒天に到着。賽ノ磧からの熊野岳・五色岳・刈田岳はいつもより大きく見えました。 大黒天からの急登も雪を被っており、いつもの階段より歩きやすく感じました。1時間で刈田岳山頂。途中から、御釜も見えています。湖面は濃い緑で、わずかにさざ波が見えますが、凍結も時間の問題のようです。来年の春まで緑の湖面を見ることはできません。山頂には、エビのしっぽが付き、樹氷の予備軍ですが、まだでき始め。遠くには、吾妻連峰・飯豊連峰・朝日連峰が見えています。 避難小屋で昼食をとりましたが、さすがに気温は低い。正午下山ですが、雪があるので歩きやすい。大黒天からは、観光道路経由で下山しました。一日中快晴で風も無い、登山日和でした。雪は例年と比べ遅いようです。
東京・埼玉・金沢の旅 2018年11月26日11月終わりの連休に、東京・埼玉・金沢を旅行してきました。 11月22日、東京・上野公園へ。フェルメール展を見ようと思いましたが、時間制の入場券になっており、夜遅い分しか残っていませんでしたので、次の機会にすることにしました。時間制のチケットでも入場まで30分かかります、というくらいの人出でした。それで西洋美術館のルーベンス展に入りました。ルーベンスは、ベルギーのアントワープで、「フランダースの犬」に出てくる、有名な教会の絵を見たことがありますが、「王の画家、画家の王」というタイトルで宣伝されていました。それにしても、東京の展覧会は人が多いので気疲れします。 時間があるので常設展を見てきました。こちらは、いつもゆっくり見て回ることができます。何度見ても、この美術館の持っている作品には驚きます。この日はセガンティーニの「羊の剪毛」をゆっくり見てきました。常設展は65歳以上なら入場無料だそうです。
翌23日は、三郷山の会のイベントで、奥武蔵の山歩き。4つのグループに分かれての集中登山です。ちょうど奥武蔵は紅葉の真っ盛りでした。鎌北湖の紅葉が見事でした。横向き地蔵も好天のもと、たくさんの登山者が行きかっています。餅つきなどを楽しみました。
24日から25日、金沢を旅しました。新幹線ができてからまだ行っていませんでした。始発のかがやき501号で大宮から乗車。停車駅は何と、長野、富山、その次が金沢です。2時間余りで到着します。早くなったものです。まだ9時前に到着。 駅を出て、近江町市場を通り、金沢城へ。さすが、加賀百万石の城でその大きさと広さに改めて驚きます。また、再建された建物で展示されていた、日本の城郭建築、木造建築の木組みの技術のすばらしさを感じることができました。ちょうど紅葉の盛りで、モミジが美しい色をしていました。そのまま、兼六園へと移動。こちらも紅葉の盛りでした。なんと、65歳以上だと、城も兼六園も入場無料!いろいろな観光地がある中で、驚きです。 兼六園は、徽軫灯籠(ことじとうろう)が名所ですが、この灯篭も紅葉の下にあり美しい。青空で風もない中、園内の紅葉と、雪つりされた松が相まって、素晴らしい景色でした。 それから、県立伝統産業工芸館、県立美術館と回りました。工芸館は、さすが金沢、といういろいろな工芸が展示されています。美術館のほうは、近く、国立近代美術館美術館の工芸館ができるとのことで、その展示もありました。 香林坊で昼食のあと、室生犀星記念館、武家屋敷、長町友禅館に寄りながら、駅前の宿に戻りました。長町友禅館はかつての友禅の作業場。加賀友禅染の行程や特徴など解説していただきました。まさに手仕事、です。一休みした後、夕方から行われる、兼六園のライトアップを見に行きました。路線バスが土日は半額の100円!。さすが観光の町です。 兼六園のライトアップは、なんと入場無料!またまたびっくり。徽軫灯籠には長い列ができていましたが。ライトアップされた紅葉が池に映る、夜の兼六園を楽しみました。土曜日に旅すると、いいこともあるわけです。 翌日は、ひがしの茶屋街、主計町茶屋街を見て、森八の菓子木型美術館に寄りました。ずらりと並ぶ200年前からの菓子の木型。そして石川県観光物産会館で、「小さな締め太鼓づくり体験」、それから城の中を通り、近江町市場近くで昼食。お土産に九谷のカップを一つ購入しました。 駅に戻り1時46分発のかがやきで金沢を離れました。富山を通るころ、剣岳はじめ北アルプスが見えますが、山頂は真っ白です。上越からは妙高や黒姫の白い姿。大宮で乗り換え白石蔵王に着いたのが18時少し前でした。4時間で帰れるとは!あまりの速さに改めて驚いた金沢の旅でした。
横柴登山口から青麻山を往復 2018年11月20日蔵王かよう会の皆さんと、できたばかりの道を通って、青麻山まで往復してきました。 スタートは、横柴登山口。遠刈田温泉から歩いて30分くらいのところでしょう。ここが標高470m。尾根につけられた道をたどり、標高641mのカタクリの丘まで登ります。先日付けたばかりの標識が、青麻山方面・北原尾方面・横柴方面を示しています。ここまで約30分。 続いて、伐採されて開けた斜面を通り、遠白分岐に向かいます。青空のもと、756山とあけら山が見えています。30分ほどで遠白分岐。ここで標高680m。このさきは、霜が降りています。 756山(しちごろーさん)の急登を十数分耐えて登ると、左側の崖が崩壊しています。注意のロープはあるものの、路肩に気を付けながら進むと、いよいよあけら山の登りです。この道は、土が洗われ、小石でじゃりじゃりの急登でしたが、右側に迂回路が作られています。こちらは立ち木を利用した快適な登山(下山)道です。 登りきって山頂につくと、そこがあけら山。展望はありませんが、820mの頂です。この山塊の最高峰です。これまで山頂にあった標識では、810mと書かれていましたが、地形図やGPSのデータにより820m以上あることがわかります。 ここから青麻山までは、1.1㎞ですが、急な笹の道を標高差100m少し下り、また登り返します。緩やかな道を上り詰めると青麻山799.5mのお馴染みの山頂です。北東方面の展望がききます。ここまで登山口から2時間余りで着きました。 帰りはこれまでの道を辿りますが、あけら山までの急登を除くと、快調に歩を進めます。756山を過ぎ、遠白分岐を過ぎ、見晴らしの良い刈り払い地で昼食。756山の下りでは蔵王連峰を眺めるビューポイントもあります。さすが11月末です、冷たい風が吹いてきます。天気は下り坂。ここから、カタクリの丘に行き、帰路は、北原尾コースを通り、途中の鉄塔から送電線の巡視路を通り横柴登山口に到着。13時過ぎ、出発から4時間半が経過していました。 距離が長そうに感じた西側の横柴登山口でしたが、2時間少しで青麻山に行けることが分かった山行でした。途中、紅葉のハウチワカエデやメグスリノキなど見ることもできました。ただ、天気のほうは、車に乗って数分後、パラパラパラと降ってきました。ラッキー!!!。
高野山・町石道を歩く 2018年11月13-15日蔵王かよう会の人たちと、高野山町石道(ちょういしみち)を歩きました。 高野山は、和歌山にある真言宗の総本山。かつてより、この霊場に至る7つの道があります。町石道はその一つで、真田幸村で有名な九度山から、21㎞を歩いて、高野山に至る道です。1町(約103m)ごとに、「町石(ちょういし)」といわれる標識が立っているのでこう呼ばれています。この町石は、弘法大師が、麓にいる母親に会うために月に9度通った道で(それで九度山)、弘法大師が1町ごとに木の標識を立てたのを鎌倉時代に石の標識に置き換えられて今に至っています。 仙台空港から出発。大阪伊丹空港で降り、南海電車で九度山に行き、泊。九度山は、真田幸村が関ヶ原の敗戦のあと不遇にも14年住んだ土地で、「真田丸」でフィーバーしました。この町について、中川旅館の主人の案内で、いろいろな遺跡を巡りました。名物の「真田ひも」も買い求めました。真田ひもで作ったお雛様もかわいいものでしたので、買い求めました。その後、温泉に送っていってもらい入浴、そして近所で夕食となりこの日は終わりました。
翌日は、朝6時半出発。歩いて15分ほどの慈尊院から町石道は始まります。ここに180町の町石があり、高野山根本大塔の1町までの21㎞、標高差800mの道のりです。 100mごとに次々に町石が現れますから、飽きずに歩けます。はじめの1/3は登り。500mほどの登りが続きます。途中でみかんの無人販売所があったり、展望台があったり、二つ鳥居という名所があったりします。昼食は宿で頼んでおいた柿の葉寿司。鯖と鮭とシイタケの寿司で酢と塩気が程よく効いておいしくいただきました。 次の1/3は比較的平らな道、そして全体の2/3が終わった矢立というところに茶店があり、ここで「やきもち」なるお菓子を賞味し、最後の登りに挑みます。途中、この前の台風で倒れた巨大な杉の木が何本もありました。後始末、大変だったと思います。一部はまだ終わっていません。 3時過ぎ、最後の急登を登り切り、大門到着。8時間かけての踏破でした。このあと、名物ゴマ豆腐を食べ、大伽藍へ。根本大塔の中の立体曼荼羅を見ることができました。 泊りは宿坊、金剛三昧院。宿坊のイメージが変わる、旅館のような建物で、精進料理をいただきました。このあたり、モミジの紅葉がきれいでした。
翌日は、バスでケーブルカー駅を経て、南海電鉄・JR・近鉄と乗り継ぎ、吉野へ。途中、昨日スタートした九度山を通過します。 吉野では、桜本坊さんを尋ね、その後昼食。そして、特別御開帳中の蔵王堂を尋ねます。堂の中にまつられた3体の蔵王権現は迫力満点。護摩が焚かれ太鼓が打ち鳴らされる中を参拝しました。蔵王のルーツの場所です。 その後、吉野駅から近鉄で帰途に就きます。途中、夕日が沈み、伊丹空港で夕食をとり、全日空のフライトで仙台空港に戻りました。
遠刈田公園の紅葉 2018年11月11日遠刈田公園は、モミジの木がたくさんあり、「紅葉の名所」と言ってもいいところです。ちょうどこの時期、紅葉真っ盛りです。 公園の中から、展望台に上る道筋、そこから、権現山の稜線を遠刈田温泉に下る山道、いずれも秋の盛りでした。紅葉の合間に、熊供養碑や遠刈田の刈田峰神社の古名、金峯山蔵王寺岳之坊の石碑などを垣間見ることもできます。
家の周りの紅葉 2018年11月9日標高300mの我が家の周りにも、紅葉は降りてきました。 今日は小雨が降り、紅葉を見るには良くない天気ですが、それでも家の周りは、モミジやナラが赤や黄色に紅葉して、いつもとは違った雰囲気です。 少し前に、紅葉のできるメカニズムを調べました。それによると、紅葉は「木々の冬ごもり」の準備だそうです。夏の間葉っぱには、緑色のクロロフィル(葉緑素)と黄色のカロチノイドが含まれ、緑~黄緑に見えます。秋になると、太陽光線は弱くなり、日照時間も短くなり、気温も下がります。光合成をするには効率が悪くなるので、葉の帥管(水や栄養が通る管)に離層という、コルク上の物質を作り、遮断します。すると、クロロフィルが光合成で作ったグルコースがアントシアニンという赤い物質に変化します。黄色のカロチノイドと赤いアントシアニンの混ざり具合で、赤~橙~黄色の葉っぱになる、というわけです。その後、落葉し、冬を乗り切るという、温帯の植物の知恵なんですね。 それはさておき、家の周りは、いい色に染まっています。 冬の準備といえば、鳥の巣箱をかけました。この春は、2個とも「住民」がいたようで、子育ての痕跡が残っていました。これから、山に食べ物がなくなると、里に降りてきて、冬を乗り切り、春には子育てをします。来春はどうなるか楽しみです。
蔵王の紅葉 2018年11月7日蔵王の紅葉も、だいぶ山を降りてきました。今年は特に紅葉がきれいに思えます。 11月5日は、エコーラインが冬眠する前の日。懸案になっていた、賽ノ磧に張ったロープの撤収に出かけました。刈田岳や熊野岳には雪が見えますが、賽ノ磧にも少しあり、冬が目の前まで来ている、という景色です。滝見台から下が紅葉の盛りで、時折車を止めて写真を撮りました。 翌日、エコーラインが冬眠に入った火曜日は、蔵王かよう会恒例の「冬の御山詣り」です。すみかわスノーパークにある蔵王山岳会の山小屋を借りてに1泊2日の御山詣り。遠刈田を10時に出て、紅葉の中を5時間かけてすみかわ小屋に到着しました。今年は、特に赤の色が強いように感じました。また、大きな倒木が4か所道をふさいでいます。そのうち、始末をしなければなりません。 翌日は、朝出発が遅れ、刈田岳までは行けずに大黒天まで往復しました。 秋から冬へ、季節は移っています。
霊山 2018年11月4日晴天がこの日まではもつ、ということで、「紅葉の名所・福島県の霊山」に行ってきました。 自宅から行くと白石市を経て福島県国見町経由で、今は伊達市になっている(かつては霊山町)霊山の登山口までは60㎞。1時間少しのところにあります。 さすがは名所、「紅葉祭り」の日曜日とあって、9時過ぎについても、駐車場はいっぱいで、路上駐車するように言われました。5分ほど登ると駐車場です。 コースは標高500mくらいのところから始まりますが、この辺りは紅葉最盛期。登山道を登っていくと、紅葉した木が右に左に見えてきます。 ここは、岩と紅葉がメインテーマ。いくつもの展望台や見どころを過ぎると、赤やオレンジの木々が見えます。標高が高くなると、紅葉はすでに終わっています。 2時間半ほどでスタート地点に戻ると、なんとトン汁のおふるまい。登山時にいただいた記念のピンバッジともども、ありがたく頂戴しました。 12時半に帰路に着きました。
蛤山と長老湖 2018年11月3日この日は、宮城蔵王ガイド協会のイベントで、「秋の蛤山に登る」に参加しました。サブガイドでした。蛤山の駐車場に8時に到着。参加者の車の整列などを行っているうちに、出発の時間9時。10数名の参加者と協会会員の20数名パーティーです。雲一つない快晴です。 林道から階段の登山道を標高差500m強登ります。伐採作業を終えた伐採地の周辺は紅葉が見事でした。ここから標高1000mまでひたすら階段の登りです。途中、ところどころで、キノコの講習会。ナメコ、クリタケなどのキノコが示されます。 2時間たって、山頂稜線。1024mの最高地点付近は倒木でまっすぐ歩けません。葉山神社のある広場で昼食・休憩。紅葉と、山頂が白くなった不忘山を見ながらの急登です。 昼食の後、下山開始。12時過ぎです。下りは、急坂の連続。17年前に開かれた国体山岳競技のために作られた道ですが、落ち葉が積もり、その下にある石や木の根を探りながら急坂を下ります。 予定より早く下山。横川の集落を通り、「横川せせらぎの里」でトイレ休憩。名物の豆腐を買い求めました。横川の川の流れを利用した漬物小屋などを見ながら、駐車場まで戻り解散。 その後長老湖に行きましたが、見たことのない景色。駐車スペースなし。大勢の観光客。ボートが数台動いていました。売店も開店、地蔵さまも檻から出ていました。これまで、シーズン中の休日の晴天の日に来たことがなかったのですが、ここは一大観光地だったのです!不忘山の山頂の雪が青空の下に見えて、周辺の紅葉とそれを映す湖、といういくつものいい要素が重なって、いい景色でした。ただ、風がなくて湖面が鏡のようであったら言うことはありませんでしたが…。 ともあれ、いい秋の一日でした。ということは、次の冬の日が来ているぞ…ということでもあるのですが。
あけら山・青麻山への道 2018年11月2日9月以来、廃道になっていた青麻山の西側の登山道の復活作業をしてきましたが、いよいよ完成に近づきました。昨日は、懸案であった、あけら山の登山道の急なザレ場を回避する迂回路を設置しました。これにより、落石が心配だった道を迂回できるようになりました。 今日は、仕上げとして、道標の設置。2つのピークと3つの分岐点に道標を設置しました。これにより、青麻山の西側から4つの登山ルートが完成です。東側の2つの登山ルートと合わせて、東西いずれからも登り、下りることができるようになりました。 写真をご覧になるとわかるとおり、西側からの登山ルートも紅葉の真っ盛り。道の途中からは、蔵王連峰も望むことができます。
長老湖と川原子ダム 2018年11月1日午前中、古道の会の皆さんとあけら山の登山道の迂回路を作る作業を行いました。これについては後日、書きます。 午後、時間ができたので、先日行ったが、天候が悪かった長老湖の紅葉を見に出かけました。今日は晴天で、多少風がありますが紅葉がきれいです。何より、不忘山が見えています。 山頂あたりに少し雲がかかっていますが、冠雪して白くなっているのが見えます。いよいよ蔵王連峰も冬の初まりです。 長老湖畔には、大型バスが停まり、中国人の団体と思しき人も来ていました。「紅葉の名所」ということです。 もう一つの不忘山を眺める湖、川原子ダムへ回ってみました。こちらは、人っ子一人いません。川原子ダムの湖水は水量がとても少なく、渇水期でもないはずですが、湖底が小さく見えていました。あいにく雲が広がり、光が当たらず、不忘山の紅葉も輝くようには見えませんでした。湖岸ではシラサギがせっせと動き回っていました。こういうこともあるでしょう。
このページのトップへ 前月の記事へ
(C)Akihiko URAKAWA
|