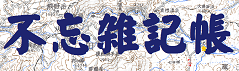|
熊野岳から中丸山 2017年6月27日蔵王かよう会の皆さんと、刈田駐車場から、熊野岳~中丸山の道を歩きました。駐車場から馬の背、熊野岳、中丸山を経て、ライザスキー場レストランへの9.5㎞の道のり。 今日の蔵王は、下から見ると雲の中ですが、朝のお釜ライブカメラでは、くっきり見えています。つまり、稜線は雲の上にある、ということで、この季節にはよくあることです。行ってみるとはたしてその通り、滝見台くらいからコマクサ平まで、雲の中です。その上は雲の上、雲海を見下ろしながらの山歩きです。 馬の背ではお釜を見ながら、途中オダマキを見て、熊野岳へ。少し下ったところでイワウメや咲き始めたコマクサを見ながら、中丸山へと下ります。途中、一昨年作られた馬の出からの避難路を合わせ、様々な花が咲いている道を中丸山まで向かいます。木道の横に残雪もありました、 中丸山の山頂を過ぎると、沢に下っていきます。ブナ林を下り、滝を見て、仙人沢にかかる吊り橋を渡ります。ここでオオルリが鳴いていましたが、望遠カメラをもたず残念。沢を登り返して、ライザスキー場に着きました。 刈田駐車場に戻ったのち、御田の神湿原を訪れると、チングルマが散り始め、ワタスゲはいよいよくっきりと見え、この3週間の変化に季節の移ろいを感じました。
後烏帽子~屏風~芝草平~刈田峠 花がいっぱいの登山路 2017年6月25日宮後蔵王ガイド協会とえぼしスキー場の共催イベントで、えぼしスキー場スタートのイベントに参加しました。 えぼしスキー場では、今シーズン、土日にカモシカリフトを運行します。ゴンドラとこのリフトを利用すると、後烏帽子岳山頂に1時間余りで立つことができます。今回は、この恩恵にあずかり、しかも、ゴールにバスが待っているということで、縦走コースとなりました。 屏風の登りのコース上に残雪がある、との情報で、先発隊としてルート工作の任が与えられたので、本隊より早く着かねばなりません。後烏帽子頂上でも、ろうづめ平でも、一休みだけで、雪渓に向かいます。屏風岳への急斜面の途中、階段のところに、20mほど残雪がありましたので、ステップを切り、念のためロープをセット。無事通過できました。 ろうづめ平から屏風岳への斜面は急ですが、いろいろな花に癒されます。シラネアオイ、オオバキスミレ、サンカヨウ、アヅマシャクナゲなどが美しく咲いています。 芝草平は、チングルマヒナザクラが満開、そして、イワイチョウが咲き始めました。刈田峠への道では、モウセンゴケ、ムラサキヤシオなどがあります。 6月末ですが、2か月ほどタイムマシンで戻ったような、花の道でした。
賽ノ磧~蔵王古道~大黒天~観光道路~新滝沢~賽ノ磧 おまけに御田の神湿原 2017年6月20日今日は、蔵王かよう会の皆さんと4時間程かけて表記のルートを歩きました。 賽ノ磧からの道は、いろいろな花が咲いています。イワカガミやツマトリソウの群落があったり、マイヅルソウで覆われていたりでした。フキノトウが綿毛になっていました。エゾハルゼミの鳴き声も聞こえています。三途の川は雪がびっしりでした。雪解けが遅いです。道にはところどころ、邪魔になる木があり、整備してきました。 大黒天で昼食。コマクサが咲き始めていました。 観光道路では、ミネザクラが満開。新滝沢ルートは、結構木が伸びており、鎌で道の整備をしてきました。 賽ノ磧に戻り、車で御田の神へ。2日前に行ったところですが、チングルマやヒナザクラは満開。ワタスゲは少し白くなっていました。オオサンショウウオのタマゴがありました。駐車場から歩いて数分でチングルマの群生が見えるところは、そんなにあるものではありません。時期と天気を選べば・・ですが。
大黒天から熊野岳そして御田の神湿原とコマクサ平 2017年6月18日今日は、天気も良さそうなので、下見もかねて、大黒天から熊野岳まで往復してきました。 高気圧に覆われる、ということでしたが、標高1000mくらいに雲がかかり、その上に行くと、太平洋まで雲海です。また、日本海側も同じで、吾妻連峰、飯豊連峰、大朝日岳山頂などが、雲海の上に見える、変わった景色でした。大黒天から刈田岳まで上る途中、雲海が五色岳に押し寄せています。 足元には、いろいろな花が咲いていますが、雪解けの遅れを感じます。コマクサは、かろうじて花をつけている株が2つありました。 熊野岳のコマクサはまだ咲いていません。大黒天に戻り、小田の神湿地に行ってきました。この前と比べ、チングルマがほぼ満開になり、ヒナザクラともども見ごたえがありました。ワタスゲは、もう少し後のようです。それでも、なかなかいい景色でした。 帰りに、コマクサ平に寄ると、ちょうど雲の中。視界10mくらいの中でコマクサを探すと、いくつか咲き始めていました。ちょっと遅れて始まった、夏の高山植物の季節です。
芝草平・御田の神湿原 花の旅 2017年6月13日今日は、蔵王かよう会の皆さんと、芝草平まで歩き、帰りに御田の神湿原を訪ねる、花の旅をしてきました。 刈田峠駐車場は、平日なのに車でいっぱい。ようやく最後のところで、駐車スペースにありつけました。小型のバスも止まっています。今日は、芝草峠往復。まあ、楽勝コースです。 歩き始めて少し行くと、雪が残っていました。今日は6月半ばなのに・・・。今年は雪が残っています。山に春が来るのが遅れています。 それでも、道端には次々と花が現れます。可憐なヒナザクラの群落、ミヤマハンショウヅルの茶色の花、コヨウラクツツジのリンゴの実のような花。ミネカエデの控えめな花、ムラサキヤシオツツジの華麗な花、タケシマランの地味な花、ツマトリソウの清楚な花、ミヤマネズの実、ミネザクラの美しい花と葉、コイワカガミの小ぶりの花、・・・・。 次々に現れる花を眺めながら、杉が峰を越えると、残雪。雪解けあとのオオカメノキは、冬芽のままです。 芝草平に来ると、花は咲き始めていました。 ミネズオウの小さい花、咲き始めたチングルマ、中には、星の形の花も。ショウジョウバカマは満開でオシベとメシベがよくわかります。ヒナザクラも満開でした。 帰りに、避難小屋でサンカヨウを見かけました。また、白いショウジョウバカマも見かけました。 峠から車で、刈田駐車場へ。そこから、小田の神湿原に行くと、1週間前にはほとんど咲いていなかったのですが、どっと咲いていました。 チングルマは、たくさん咲いていました。ワタスゲも、白くなりはじめ。そしてヒナザクラの大群落。あと1週間で、花のピークになりそうです。もう、6月半ばですからね。九州から関東は、梅雨の季節です。
そらまめまつり 2017年6月11日隣の村田町でやっている「そらまめまつり」を覗いてきました。 道の駅、村田が会場ですが、駐車場に入る車の行列ができています。この列に並ぶ気がしなないので、さっさと第2駐車場に向かいました。正解でした。 会場に行くと、テントがいくつも出ています。一番最初は、焼きそらまめの無料ふるまい。一ついただきました。次のテントは、そらまめの箱での販売。Lは売り切れていました。Mで一箱3000円。 奥のテントは、500円でそらまめ詰め放題。やってみました。とにかく袋に乗っていればいいのです。 売店には、「ドレミファそらまめまつり」のポスター。覗いてみると、数々のそらまめ製品。おかし、米粉麺、焼酎、こんにゃくと多彩です。 渋滞は続いていますので、早々に撤退しました。今夜は、そらまめをつまみに、ビールといきましょう。
熊野岳・地蔵山 2017年6月6日馬の背稜線を通り、熊野岳、地蔵山を歩いてきました。 刈田駐車場から馬の背までは、まだ雪が残っています。馬の背に出て、お釜を見ると、この前見たような、抹茶色の湖面。これまで見た、エメラルドグリーンではありません。何が起こっているのでしょうか。 熊野岳の山頂にある、熊野岳神社には、よく見ると、役小角の石仏や、蔵王権現・金峯山などと書かれた石碑がありました。これまで何度も来ているのに、よく見たのは初めて。 熊野岳を超えて、ワサ小屋跡に降りる岩の道では、コゴメツガザクラやミネズオウの花が目立たないながらも咲いています。イワカガミはまだつぼみ。 ワサ小屋跡に来ると、山姥の石像が立っています。この石像、首のところでつなぎ合わされ、胴体の古さに比べ、怪異な頭の部分が新しいのですが、説明書きによると、頭は積まれた石の下に埋もれていたのを、今から6年ほど前につなぎ合わせたそうです。 地蔵山から、ロープウェーに下りる途中には、ミネザクラが咲き、アカミノイヌツゲがありました。また、アオモリトドマツが枯れ死の状態です。トウヒツヅリヒメハマキという蛾による被害ですが、収まったのでしょうか。3月に来たときは、樹氷がやせていたのを思い出しました。 お地蔵様の前のベンチで昼食のあと、帰途に就きます。雲は飛んで、地蔵山では、月山、鳥海山が見えていました。熊野避難小屋を経て、馬の背を通り、刈田駐車場へ。その後、御田の神を見に行きましたが、花は少なく、わずかにヒナコザクラ、ミツバオウレンがあっただけで、チングルマはもう少し後のようです。 山行中に、イワヒバリとカッコウを見ましたが、望遠のカメラを持っていかなかったので、シルエットだけの小さな写真になりました。
疣岩分水工 2017年6月5日6月になりました。今日は、かねてから気になっていた、「疣岩分水工」(いぼいわぶんすいこう)を見に行きました。 これは、蔵王町の、役場から遠刈田に行く県道の途中、疣岩(いぼいわ)の近くにある、農業用の灌漑施設の名前です。道路のすぐそばなのですが、駐車スペースがないために、これまで素通りしてきました。 これは一体何か?蔵王町のWebページによると、次のように説明されています。 (http://www.town.zao.miyagi.jp/kurashi/kurashi_guide/sangyo_kensetsu/nourin/bunsui.html) 「疣岩分水工は円田字棚村地内の県道沿いにあり、現在の農業振興の基盤として重要な施設で、県内では一番最初に出来た分水工と言われています。 遠刈田発電所で発電用に使った澄川の水の一部をこの分水工に放流し、7割が澄川用水路に、3割が黒沢尻用水路の方に分水され、850haの水田に活用されています。」 写真を見ればわかるとおり、発電所から中央の湧き出し口に送られてきた水を、周の長さの比7:3に分ける仕組みです。これなら、水量が多くても少なくても、同じ比率に分けることができます。この水が、蔵王町だけでなく、村田町、大河原町の広大な農地を潤しているわけです。掲示板によると、澄川用水が975ha、黒沢尻用水が1003haだとあります。 また、蔵王町観光物産協会のWeb(http://www.zao-machi.com/16560)では、 「時代をさかのぼること約百年前、大正初期のこの時代は毎年干ばつに見舞われ、旧円田村、村田町などの地域は、農作物を栽培するための水不足に悩まされてきました。『我らに水を与えよ。しからざれば死を与えよ。』と村人たちが嘆くほど干害による被害が続きました。村人たちは新たな水源として澄川に水を求め、分水施工から完了まで2年を要したこの施設は、80年経った今もなお使われています。」 「この分水工、昭和6年から運用され、今も現役で使われています。 平成23年、公益社団法人土木学会により、選奨土木遺産(昭和初期までの時期に建設された近代的な土木構造物で、当時の技術や地域の近代化のようすを今に伝えることができるものに対して土木学会が認定するもの)に認定されました。」 と書かれています。その昔、先人たちが農業に必須の水をどのように確保してきたのか、というのを物語る施設なのですね。上流にさかのぼれば、遠刈田大橋の上、澄川と濁川の合流地点で、澄川の水だけを、水力発電所に引き、その発電の仕事を終えた水を、今度は、農業用の水として、2つの地域に決まり通りに分けて、諍いをなくしているのがこの施設なのです。先人の知恵を感じます。 近所の果樹園では、桃、梨、イチジクが実をつけ始めていました。
このページのトップへ 前月の記事へ
(C)Akihiko URAKAWA
|