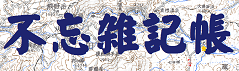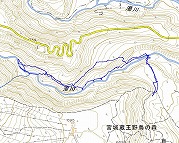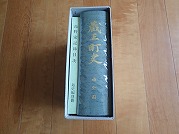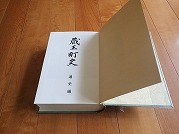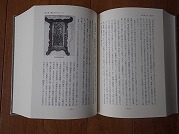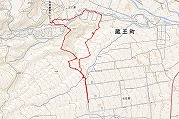|
�g�t�̎O�K��@�@�@�@�@ �@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@2016�N10��31���@�O�K�ꂠ����̍g�t���f���炵���̂ŁA�����́A���쉈���ɎO�K��܂ōs���Ă��܂����B �@���ƐX�N���u�������ѓ����l�ߒ��ԏ�ɍs���A����ɉ����u���k���R�����v�ɉ����čs���܂����B���̑O������Ă��܂�������̋��ł����A�X�����ɍs�����H���ŁA���h�Ɋ|���ւ����Ă��܂����B �@���̂�����̍g�t�������ł��B���ɁA���O�X���m�L������Ƃ���ł́A�Ԃ��������B����n���đΊ݂ɍs���ƁA���͐̂̂܂܂ł����B���R�̉Ƃō�������W�����Ȃ���A���ݐՂ�T���ĕ����܂����B���J�����ō����������āA�O�K��ɒ����܂����B�n����Α��ɍs���܂����A��߂ɂ��āA�I��o��A���쌤���H�ɏo�܂��B���̐�͓����������Ă���悤�ŁA��������֎~�B�@�r�����{���|������A���z���āA���R�̉Ƃɖ߂铹�����܂��B���蕥���͂���Ă��炸�A�r���̕����K�i�͂��̂܂܂ł��B������A�ꕔ���M������Ԃł����B����́A�����ȍg�t�ł��B �@�Q���Ԕ����炢�ŎԂɖ߂�A�g�t�̐^������̐�����ӂ�����Ă��܂����B
�G�R�[���C���̍g�t�@�@ �@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@2016�N10��29���@�P�O�������ɂȂ�܂����B�����������ɂȂ�A�G�R�[���C���̗l�q�����ɍs���܂����B �@�ꌩ�䂩��s�����A�������������肪�g�t�^������ł����B�s����́A�g�t�̒��Ő��ʂ������A�����ł����B �@�������́A����X�L�[��̂����肩��́A�t�͗����āA�~�͂�̗l���ł��B���̓��́A�单�V�����͉_�ɕ����A���c���͉_�̒��B�C�����P���ŋ������������Ă��܂����̂ŁA�n�m�w�ɂ�����̂͒f�O�������Ă��܂����B���݁A�G�R�[���C���͖�Ԓʍs�~�߂ɂȂ��Ă���A�Q�[�g���܂�̂ŁA���̃Q�[�g�܂ł̋����̕W�������Ă��Ă��܂��B�܂��A���t�̏����Ƃ̂��߂̃|�[�����S�������ς݂ł����B �@����X�L�[��ɖ߂�ƁA�u�W�]��v�̊Ŕ�����A�i��ł݂�ƁA�X�L�[��̌����̏�ɁA�u�����킭�e���X�v�Ƃ����W�]�䂪����Ă��܂����B�_�͒Ⴂ�ł����A�͂邩�����܂Ō����Ă��܂��B�f���Ă݂�ƁA����I�[�v�����Ƃ��B���̂�����̖���������������ł��B�����������āA���쌹���̃r���[�|�C���g�́A�g�t�^������B����ߗ��̊����������ƌ����Ă��܂��B �@���̌�A�K�C�h����̕��Ɖ�A�n�m�w�Ő��̗�������֎~�̃��[�v������ɍs���A�Ǝf���A����`�����邱�ƂɁB�Ăъ��c���ԏ�܂Ŗ߂�A������Ŕn�m�w�Ő��ɏオ��܂����B�r���A����ꂪ�~��A���X�������Ă��܂����B���������A���܁A������Ƃ��Ȃ���A����������̃��[�v������B���������Ɣn�m�w��P�ނ��܂����B���������A�����^�~�ł��B �@�G�R�[���C��������A���H���������A����ňꕗ�C���т܂����B�~�͂����܂ŗ��Ă��܂����B
�Ƃ̎���̍g�t�@�@ �@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@2016�N10��27���@�g�t�������ԉ���Ă��܂����B�Ƃ̎���̖X���F�Â��Ă��܂��B �@�^���m�L�A�k���f�A���~�W�Ȃǂ́A�F�������܂���B�c���o�i��u���[�x���[�͐F���N�₩�ł��B �@�������A���N�̍g�t�ɔ�ׂāA�F�������܂���B�،͂炵�������܂ł���1����B�g�t�̎����������܂��B
�g�t�̈��B���ǎR�@�@ �@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@2016�N10��11���@���B���ǎR�̍g�t�����ɍs���܂����B�R�[�X�́A���[�v�E�F�[�œo��A���B���ǎR���A��̒҂��o�R���ăN���K�l�����A�����ē���k�J�����R������ɁB�S�l�ŎԂR��Ƃ����g�ݍ��킹�ł��������R�n�̉���X�L�[��̒��ԏ�ɎԂ��Q��u���A���x�̒��ԏ�ւV���S�T���ɓ����B���[�v�E�F�[�͂W�����^�s�J�n�B����ő҂��Ă���ƁA�o�����ɂ͒��ւ̗�B�����̍����ł������̗l�q�ł��B����͂����������悤�ł��B �@��t�x�̉w����́A�g�t�̐^������B�����������Ă��܂����̂��c�O�ł����A�g�t�����Ȃ���P���ԗ]�ŎR���ɒ����A�R������̌i�F�����\���܂����B�������A�����B���������āA���H��Ԃ̊����ł����B �@���̔w��ʂ�A�^�����ȕ��Ό������܂����B���������͕ʐ��E�̂悤�B��̒҂��o�ăN���K�l�����ցB��������A�g�t�̒��̓��ł����B �@�N���K�l�����Œ��H�̌�A���R�J�n�B�����s�����Ƃ��납��A����k�J�ւ̓��ɓ���܂��B������̓��́A�k�J�����ŁA�㗬�ł͐��x�̓n�A�Ƃ����Ă��A���͉˂����Ă��܂��B�������A�ۑ����R�{���˂��̂��A��ꂩ�������̂��ƁA�X�������_�B�܂��r���ʼn��x���A�w�c���⍂�����̘A���B�������������̂��A�k�J�̍g�t�ɂ͏��������悤�ł����B���J�����œ������A�N�T����[�v�𗊂�ɓn���Ă䂫�܂����B �@�Q���߂��ɉ���X�L�[��ɓ����B����ňꕗ�C���тāA�Ԃ�������A�����c�̖߂����̂͂T���ł����B
�������j�@�@�@�@ �@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@2016�N10��8���@�ߓ��A�u�������j�@�ʎj�ҁv�Ȃ�{���w�����܂����B�Q�O�N�قǑO�ɏo�ł��ꂽ�A�������̒��j�Ҏ[�ψ���ɂ��S�S���̒��j�̓��̂P���ł��B �@�����Vcm�ƍL�������Pcm�������̓��X�Ƃ����{�ŁA�t�^�̍��q������ƍL�����Ȃ݂̔��ɓ����Ă��܂��B�d������������ł��B�y�[�W���͂P�Q�P�S�y�[�W�A�̔����i�R�O�O�O�~�ł����B �@���e�́A���̎��R�A���j���A���n�Ñ�E�����E�ߐ��E�ߑ�E����A����ɁA���ʕ҂ő����M�j�Ƃ������A�Ă���̓��e�ł��B�ς�ς�Ƃ߂���܂������A���낢��Ƌ����[�����Ƃ�������Ă��܂��B �@�~�̖钷�̎��ԂԂ��ɗǂ������Ȗ{�ŁA�y���݂ł��B�Ȃ��A�ʎj�̑��ɁA�����҇T�E�U�A�����҂�����܂����A����́A�ʎj�҂̂ݍw�����܂����B�K�v�ɉ����āA�}���قłł��ǂ݂����Ǝv���܂��B
�k�����c���@�@ �@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@2016�N10��5���@�K�C�h����݂̂Ȃ���ƁA�k�����c���H������܂����B���̏c���H�́A�u���v���Ȃ��ƕ����Ȃ��Ƃ���ŁA���}�o�X�̎�z������܂����B�����S�O�l�̑啔���ł��B �@�W���߂��Ɋ��c�x���X�g�n�E�X�o���B�n�m�w��i�݂܂��B�E��̑����m���͉_�C�B�䕗�̉e���Ǝv���铌���������Ă��܂��B���낤���āA�����͌����Ă��܂������A���̌�A�_�̒��B �@�F��x�����̘e��ʂ�A����ɂ�����܂��B���R����ʂ薼������߂����܂��B�r���A�E���ɉ���镪����������߂��A�P�O���߂��A������ցB �@����ɒ�����艺��̓����o�āA�P�Q���O�ɁA�����������B�����́A��蒬�̌��Ă����h�ȏ����B�S�O�l�͊y�ɔ��܂����K�ȏ����ł��B�c�O�Ȃ̂́A����܂ʼn������ƁB�Ԃǂ���ɂP�W�����肽�Ƃ���ɂȂ邻���ł����A����ł́A�����݂��P���Ԏd���B �@���H����������ƁA��ˎR�̓o��B�}�ȓ������߂�ƁA���ˎR�B��u�A�����̎R�`�����̎R�X�������܂����B�}�ȉ���̂��Ɠo��Ԃ��āA��ˎR�B�R����O�ɁA����V���̕�����܂��B��ˎR�ł��A��u�W�]���J���܂����B�܂��͍g�t�ł��B �}�ȉ�������肽���ƁA���̃s�[�N�͌������B �@�����āA�֑�A�֑�W���ɂ���܂��B��^�o�X�����J���܂œ���Ȃ��̂ŁA�֑�̃C���^�[�߂����I�_�B�r���A�A�N�V�f���g���������肵�āA�o�X�̏o���͂T���P�O���B�ӂ�͂�������Â��Ȃ��Ă��܂����B�H�̓��͒Z���A������������āA�P�Ukm���܂�̏c�����I���܂����B
�쑠���c���H�`������܂Ł@�@ �@�@ �@�@�@�@�@�@2016�N10��4���@���悤��݂̂Ȃ���ƁA�쑠���c���H������܂����B���̓��́A���B������C���ɋ����������������݁A�c���H�͕��̒ʂ蓹�B �@���܋����Ɍ������Ȃ���A�g�t�����c���H��i�݂܂��B�ꕔ�̃~�l�J�G�f���I�����W�F�ɂȂ��Ă��܂����A���܂�F�͂����܂���B�i�i�J�}�h���������ɂȂ��Ă��܂����B �@�O�R���߂��A������܂łł��̓��͓P�ށB�g�t�����Ȃ���A���̒���߂�܂��B �@���c���̔����Œ��H�B�O�͕��̉��B����S�ł��B�V���^�}�̎��ȂǁA����̏H����������̂�����܂��B���ƈꌎ�ŁA�R�͓~�x�x�ł��B
�σ��X�@�@ �@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2016�N10��2���@�������R�̉Ƃ���A�n�[�g�����h�֍s���R��������A������u�σ��X�R�[�X�v�ƌĂ�ł���悤�ł��B�����́A���̓������ǂ��Ă݂܂����B �@���Ƃ�͂������瓹�H�ɏo�āA�����o���������ɁA�����̏����ȕW��������܂��B�������X�^�[�g�B���ɓ���ƁA�����ɉ�����n�鋴���˂����Ă��܂��B��������A��100m�̋}�o�B���[�v�������Ă��܂����A�����͔S�y�ŁA�o��͉̂��Ƃ��Ȃ�ɂ��Ă��A����́E�E�E�ƍl���Ă��܂�����̘A���ł��B �@�悤�₭�o���ƁA��������ɂȂ�A�u�i�т��L����܂��B���X�ɁA�u�σ��X�v�Ƃ����W���ƁA�u�����R�̉Ɓ@�n�[�g�����h���v�̓��W�B���x�͋}�ȉ����̂��ƁA���n��A�т̒��̓����㉺���Ȃ���i�݂܂��B���X�|������܂����A�����₷�����ł��B���ꎞ�ԂقǍs���ƁA�����ǂ̋��B�������ɑ��������{�݂ł��B����ɉ����đ�𐔉�n��ƁA�������ܑ̕����H�B���炭�s���ƃn�[�g�����h�B �@�����܂ŁA�}�����łP���ԁB�܂�Ԃ��߂�܂��B�r���A�E�ɓ��������A�т̒���i��ł����ƁA�ʑ��n�ɏo�܂��B�������瓹�H�Y���Ɏ��R�̉Ƃɖ߂�܂��B�悭���܂ꂽ�A�̂���̓��ł����B �@���፷140m�A����6.5km�̓��ŁA�������̂ɂQ���Ԃ�����܂����B�������̉��ɂ́A���������̂���g��ꂽ�������낢�날��悤�ł��B
���̃y�[�W�̃g�b�v���@�@�@�@�@�@�@ �O���̋L����
(C)Akihiko URAKAWA
|