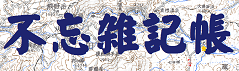雪が降った 2015年1月31日昨日朝から降った雪は、夜にはあがりました。朝には、青空の下、30cm位の積雪で、辺り一面銀世界。家の前の道も除雪してくれましたが、車を出すには、雪かきが必要でした。 昨年の大雪では、雪かきの道具が活躍しましたが、今年は、これに加えて、「ダンプ」という道具を用意しました。スコップと違い、足を使って雪を大量に運べるので、効率は上がります。昼までに、車を出せる状態にしました。 午後は、運動不足解消をかねて、近くのサイクリングロードと遠刈田公園にスノーハイキング。山に入ると、キツネでしょうか、足跡が転々と。 小一時間歩いて、共同浴場で温泉につかり、帰宅しました。
えぼしスキー場の花火大会 2015年1月25日昨夜、えぼしスキー場で、恒例の花火大会が行われました。昨年は、こけし橋から見ましたが、今年は、スキー場へ行き、間近なところで見てきました。 7時から開幕なので、6時過ぎに出かけていくと、入口で700mの渋滞。駐車場はかなり埋まっていました。 ゲレンデに行くと、7時少し前。時間になると、「たいまつ滑降」が始まりました。といっても持っているのは、たいまつではなくLEDライト。でも、エンジ色の灯りがすてきでした。 続いて、花火の打ち上げ。いろいろな花火を雪の上で楽しみました。この時期にしては、風もなく穏やかな、過ごしやすい花火見物でした。 帰りは、混みそうなので、少し早く会場を出て、遠刈田温泉でかじかんだ体に一風呂浴びて戻りました。
宮城蔵王の刈田峠の樹氷原に行ってきました。 今年は、例年より早いらしく、立派な樹氷ができていました。「アイスモンスター」の異名を持つ樹氷。この日は、風はあまりありませんでした。天候は残念ながら青空、とはいきませんでしたが、樹氷を楽しむことができました。
後烏帽子岳に登る 2015年1月21日今日は、高気圧に覆われ、夕方までは穏やかな天気が持ちそうだったので、リフトを使って、後烏帽子岳(1681m)に登ってきました。 コースは、えぼしスキー場のゴンドラとカモシカリフトを乗り継いで、1350mのカモシカリフト終点がスタート。そこから、高低差330mの登りです。夏道ですと1時間半くらいですが、冬は、雪の状態に左右されます。 カモシカリフトを降りて支度。先行者のつけたトレースがあります。スキーの跡と、スノーシューの跡です。積雪は1mほどありますが、意外としっかりした雪で、スノーシューではかどります。途中から、夏道に合流しました。風もなく、穏やかな天気が続いています。途中、巻層雲が空を覆ってきました。 途中から樹林を抜け、展望が見え始めました。仙台平野・太平洋方面です。50分ほど歩くと、先行する3人組、降りてきた単独行者とすれ違い、1時間15分ほどで山頂へ。 さすがに山頂では、風が冷たく吹いていますが、目の前にある真っ白な屏風岳の壁、その左に遠く不忘山、近く馬ノ神山が見えています。また、屏風の右側には、真っ白な刈田岳と熊野岳、その右には月山でしょうか。さらに右には雁戸山の真っ白な尖った峯が印象的です。 景色を見た後、冷たい風に追われるようにして下山開始。途中、昼食を挟んで、1時間ほどでスキー場へ。そこから、ゲレンデの端を歩いて2時過ぎに降りてきました。 途中、カモシカの足跡や、樹氷のアカチャンのアオモリトドマツなどが目を楽しませてくれました。 下山して、遠刈田温泉で一風呂浴びて、空を見ると、後烏帽子の頭には、雲がかかっていました。ラッキーな時間でした。 反省が2つ。カメラを持って行かなかったので、iPhoneで撮りました。画質は悪くないのですが、手袋をしたままでは撮れません。寒い思いをしました。冬はだめですね。もう一つは、サングラスを車の中に忘れてしまい、ゴーグルは家に置いてきてしまいました。巻層雲が出て、陽射しがなかったのが幸いでしたが、冬山のサングラス忘れは致命的ですからね・・・。反省。
冬の夜空には、きらきらと星が光っています。都会にいるときには見ることのできなかった星空です。 昨年も、星空の写真を撮って、この雑記帳に載せましたが、ある先輩よりメールを頂きました。彼は、自分で天文台を持とうとしている、アマチュア離れした、天文ファンで、「せっかく空気のいいところに住んでいるのだから、ちゃんとした写真を撮りなさい」とおしかりを受けました。 様々な写真を撮って来ましたが、鳥の写真と星の写真について、技術や機材など難しく、満足のいく写真が撮れないでいるのが原状です。 少し勉強して、夜空の写真を撮りました。オリオン座と昴です。昨年のよりもよく撮れていいると思います。飛行機か人工衛星か何かも写っていました。 冬の夜は、寒くて大変ですが、もう少しましな写真が撮れたらいいなと、今後の課題です。
遠刈田では、1月14日の小正月に、「ちゃせんこ」という行事が行われます。 夕方、子供たちが、家々をまわり、 「あきぃーのほうから ちゃせんこにきぃしたぁ〜」 と唱えると、その家の人が人数分のお菓子などを、子供に配るのです。 子供たちは、何人かでグループをつくり、一杯にお菓子が入った大きな袋を持って、町中を歩き回っています。 なにやら、欧米のハロウィンに似ています。 子供たちは、「明の方から ちゃせんこに来した」と言っています。 「明きの方」とは、その年の歳徳神(陰陽道で、その年の福徳を司る神)のいる方角で、恵方巻の恵方と同じです。今年は西南西とのこと。 「ちゃせんこ」というのは、宮城県の他の地方では「ちゃせご」ともいっているようで、昔の子供が髪の毛をてっぺんでしばると、茶筅に似ているので、ちゃせご、ちゃせんこと言ったとか。 250年前から行われている行事で、昔は、厄年の人がいる家で、厄落としのために、福を運んでくる子供たちに、餅などを配っていたようです。 子供たちは、数ヶ月分のお菓子をゲットして、嬉しそうでした。石巻の方でも行われているようですが、こちらの方では、遠刈田だけに伝わっている行事だそうです。いいですね。私もおこぼれにあずかりました。 さて、東北地方で行われているのが、どんと祭。正月飾りを神社に納め、燃やします。この火にあたると、息災になるとかで、遠刈田の、刈田嶺神社でも行われました。
時々利用している、東北本線白石駅の1番線ホームには、煉瓦造りの小さな建物があります。この建物の前にある、説明書きによれば、次のように書かれています。 この赤煉瓦の建物は明治二十年十二月十五日、白石駅がこの地に営業開始とともに灯火類の油を収納する油庫として建築されました。 東北本線白石駅開業時に建設された唯一駅構内に残る貴重な建物です。 ということで、歴史的な建物ですが、いつもは、扉が閉ざされています。どういうわけか?今日は、扉が開いていて、中の展示物が見学できるようになっていました。 入ってみると、「白石駅ギャラリー」ということで、いろいろな鉄道関係のものが展示されています。 各時代に使われてきた、珍品の数々です。かつての時刻表、標識、鉄道模型、駅の模型、時計など、鉄道ファンなら垂涎の品々です。特に目をひいたのは、腕章。「伝令者」とか、「防疫」など、どのように使ったか想像しがたいものもあります。 今日は、時間があまりないので、ざっと見ただけですが、時間があれば、一つ一つ時間をかけてみたいものです。ただ、いつ開いているのだろうか?
前日1月5日、車で出かけて、家に戻ったとき、家の前の道路を、2羽のヤマドリが横切りました。急いでそこに行ってみると、雪の上に、足跡が残っていました。初めての遭遇です。ヤマドリは、藪に中に入ってしまい、写真には撮れませんでした。 翌6日、「ことりはうす」のエサ台近くで、ヤマドリを見かけました。何でも、ここには毎日のように来ているそうです。 ついでに、ことりはうすに保管している、ヤマドリの剥製の写真を撮ってきました。
家の前の林の中で、リスを見かけました。木から木に、素早く飛び移り、時々何かを食べているようです。これから、本格的な冬の季節の訪れです。冬眠しない彼らも、食べ物探しで、大変ですね。
2015年、新しい年が始まりました。 年の初めに、仙台の街に出かけました。 1月1日は、元朝参り。大崎八幡神社に出かけました。1日は、街の中心部も静かですが、神社の周りだけは活気があります。参道の途中に、雄勝町の牡蠣小屋がありました。とても混んでいたので、眺めるだけでしたが、4年目になるというのに復興未だし、という思いです。甘酒の振る舞いなどもありましたが、こちらも混んでいて、見るだけ。社殿の前は、ずらりの人。帰りに、青葉神社にも寄りましたが、こちらも、社殿の前は行列でした。 2日は仙台名物の初売り。町中は、かなりの人が出ていました。いくつか買い物をして、遠刈田に戻りました。
このページのトップへ 前月の記事へ
(C)Akihiko URAKAWA
|