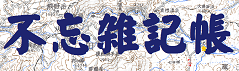不忘山・ユキワリコザクラの山 2015年5月26日今日は、蔵王連峰の最南端、不忘山に登ってきました。白石スキー場からのコースです。遠刈田の登山愛好会のみなさんとともに登りました。 標高約850mの白石スキー場を出発し、1705mの山頂までの標高差850mのコースです。スキー場から、白石女子高山小屋跡まで行く途中、アサギマダラを見かけました。飛んでいる姿を写真に納めるのは難しいのですが、なんとか写真になりました。 登山道の入口には、火山情報と規制の看板。スキー場から登山道を辿ると、春ゼミの鳴き声の中を標高を上げていきます。サラサドウダン、シラネアオイやタムシバの花が咲いています。 山頂近くになると、ムラサキヤシオツツジ、ミヤマキンバイ、ハクサンイチゲの花々。そしてお目当ての、ユキワリコザクラの花が登場します。山頂近くに群生し、小さな, あでやかな姿です。向かいの屏風岳には残雪が残っています。山頂では、キアゲハが舞っていました。また、越冬したらしい、羽の壊れた蝶がいました。帰宅後調べてみると、「ベニシジミ」でした。花の山不忘山の面目躍如です。 帰りにスキー場で、山菜摘みをして、帰途につきました。 追記:最後の蝶の写真「ベニシジミ」と書きましたが、「ヒオドシチョウ」のようです。指摘していただいた、J.Y.さん、どうもありがとうございました。
緑のカーテン 2015年5月21日好天が続き、昼間は暑い日もあります。季節は、春から初夏へと移っています。 昨年に続いて、西側の窓の前に、「緑のカーテン」を作りました。昨年は、プランターで育てたせいか、生育が今ひとつだったので、今年は、路地植えに挑戦。といっても、そのままでは、山砂のやせた土なので、花壇のように作ってみました。 ホームセンターで、コンパネを一枚購入。これを裁断してもらいました。長辺に沿って、幅22cmの四枚の板を作り、それらを、40cmと140cmに切ってもらいました。これを金具で組み立てて、二組の「底なしの箱」ができます。地面に置いて、腐葉土を入れます。これで「花壇」のできあがり。費用は、コンパネ1500円、金具1500円の3000円。 今年は、この2つの「花壇」に、ゴーヤ、ツルありインゲン、キュウリの苗を植えてみました。どれが育つのか、実験をかねてです。水をたっぷり掛けます。そのあと、去年、壁につけてもらったフックを使って、網を張りました。これで準備完了。 それとは別に、二種類のカボチャの苗を植えてみました。雑草の中で、カボチャがどれくらい育つのでしょうか。 ということで、今年の「緑のカーテン」は準備完了。しばらくは、水やりを欠かせない日々です。
細倉マインパークと細倉鉱山資料館 2015年5月18日栗駒山山開きの日は、少し下がったハイルザーム栗駒に泊まり温泉でゆっくり。今日、帰りにかねてより気になっていた、細倉鉱山あとに作られた施設に寄り道をして戻ってきました。 細倉鉱山は、1987年まで操業をしていた、鉛、亜鉛を中心とする鉱山で、その歴史は1000年以上と言われています。昔仙台で暮らしていた頃、名を聞いたこともあります。今はその坑道の一部が、観光施設になっているとかで、それが「細倉マインパーク」です。 震災後の特別料金とかで、半額になっていました。坑道に入ると、ぐっと気温が下がり、あとは19℃くらいで一定に。ここに、操業当時の資料や、歴史的な採掘の資料、そして、後半はタイムトラベル・歴史探検の旅と銘打ち、様々な展示がされていました。子供たちが喜びそうです。また、3年間酒を預かり、熟成させるというザービスもしているようです。 誰も客がいなかったので、すんなりと全部回れて、30分ほどで出口へ。ここは、お土産物や鉱物を売る売店でした。 次に、近くの鉱山資料館に行きました。三菱マテリアルの工場の向かいにある建物で、ここでは、鉱山閉山後、使用済みのバッテリーから、金属を取り出し、再生しており、鉱山操業時より多くの量を扱っているとの話を伺いました。30分ほど、当時の鶯沢町が作ったビデオを見て、概要がわかりました。そこから、4室にわたる資料室を見ると、歴史、技術、鉱物などの展示がされており、当時の様子を偲ぶことができました。 どちらの施設も、他に客がいず、若干寂しいような気もしましたが、ゆっくり見学できました。 帰りに、栗駒木材の工場に寄り、冬のストーブの燃料の木質ペレットを300kg購入し、ゆるゆると高速道路を走り、自宅に戻ってきました。
栗駒山・山開き 2015年5月17日5月17日は、栗駒山の山開き。朝6時、蔵王の自宅を出て、高速道路を走ると、8時半にはイワカガミ平に到着しました。山開きの行事が行われていました。御神酒も配られました。ちなみに、この時刻だと、イワカガミ平の駐車場は満車で、その下の駐車場からのシャトルバスのお世話になりました。 東栗駒コースは積雪が多いとかで、中央コースを取ります。歩き始めに、雪渓。少し歩くと雪はなくなり、夏道を辿ります。白いコブシが道の左右に。あるものは咲き終わり、あるものは蕾。少しあがると、ミネザクラ。こちらはちょうど咲きそろった頃。天気はよいが、風が少々。1時間少しで山頂直下に。ここから、山頂まで雪渓が続いています。その長さ約500m。アイゼンを履いて、山頂へ。出発から1時間45分で山頂に着きました。 山頂では、時折強い風の吹く中、大勢の人が食事中。急いですませて下山開始。雪渓を注意して下り、あとは、中央コースのよく整備された石の道を下ります。ちょうど中間地点に、儀式で使われた、馬ノ神輿が山頂を向くように置かれていました。担ぎ手たちは、ここから、空身で登ってようです。時折、ミツバツツジの花もありました。 イワカガミ平に到着後、シャトルバスで下山。途中には、2mほどの雪の壁もありました。
えぼしのシロヤシオ 千年杉と白龍の滝 2015年5月11日えぼしスキー場のあたりはシロヤシオツツジの群生地として有名な場所です。花が咲き始めたとの話を聞き、行ってきました。 えぼしスキー場の駐車場から、千年杉コースを取って、ゆっくりとブナ林を登っていきます。ちらほらとシロヤシオツツジが見えてきます。足元には、ブナの花が散らばっています。1時間ほどで千年杉。「森の巨人たち100選」というのに選ばれている大木で、樹齢は600年、幹のまわりが6mあるそうです。1年に1cmの勘定。 「森の巨人たち100選」とは、2000年4月に林野庁が全国の国有林の中から、100本の巨樹・巨木を選んだそうです。条件は、地面からの高さ1.2mのところの直径が1m以上あり、地域のシンポルとして親しまれていること。 そこから上に行くと、ますます、シロヤシオツツジが多くなってきます。ムラサキヤシオツツジもちらほら咲いています。また、春を告げる花、シヨウジョウバカマやオオカメノキの花。ゴンドラ駅まで登ると、ホシガラスがさかんに飛び回っていました。水仙の花もまだ残っており、山腹の淡い緑も見物です。後烏帽子岳の沢筋にはまだ雪が残っています。 下りは、石子自然観察路経由です。途中、白龍の瀧を通り、2時間弱で駐車場へ戻りました。例年より早い、シロヤシオツツジの花でした。
連休 2015年5月3日5月のゴールデンウィークとなりました。 3日は、気にかかっていた、タイヤ交換。冬タイヤから夏タイヤへ交換しました。 車2台分8本です。 家の周りは、赤いツツジが、ここにもあるよ、こっちにもあるよと、存在を主張しています。この日、知人が訪れ、境界までの草刈りをしてくれました。「恐るべし、機械の威力」
5月の蔵王 2015年5月1日5月に入り、好天が続いています。松川には、今年も、鯉のぼりがかかりました。背後の山脈の残雪も、だいぶ少なくなっています。 家の周りでは、ツツジが咲き始めました。また、昨年、種から育てているブナも無事冬を越し、10cmくらいになりました。昨年植えたブルーベリーにも花がびっしりついています。今年は収穫ができるでしょうか。竹をもらってきて、野鳥の水飲み場を作ってみましたが、果たして、お客は来るでしょうか? のどかな日々ですが、一方では、蔵王火山の噴火予報などとともに、慌ただしく対策が行われている、5月のはじめです。
このページのトップへ 前月の記事へ
(C)Akihiko URAKAWA
|