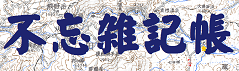|
月山の紅葉はスゴイが雲の中 2018年9月28日この日は天気が良さそうなので、月山に行きました。高速道路が一直線に延びているので、家を出てから1時間半で登山口の姥沢駐車場に着きます。途中、蔵王は山頂が見えていましたが、月山の山頂部は雲の中。 リフトで登っていくと、紅葉しています。リフト上駅も雲の中。8時半出発。牛首までは、草紅葉。それを過ぎ、急な登りにかかるとミネカエデが色づいています。同じミネカエデでも赤いのや黄色いのと色が違います。光が当たればさぞかしキレイだろうに・・・。 2時間で山頂。神社は営業しておらず、無料で最高地点に行けます。また、神社の先、弥陀ヶ原の方に少し行くと、一等三角点があります。山頂で昼食をとり少し粘りましたが、雲は取れません。 11時に下山開始。方位盤があるのを初めて知りました。牛首から姥ヶ岳経由で下ります。姥ヶ岳周辺もミネカエデが見事な色をしています。姥ヶ岳を降りる頃、1700mより下が見えてきました。リフト上駅周辺も見事です。さすがに花はほとんどありませんが、リンドウがたくさん見られました。季節外れのハクサンイチゲもちらほら。リフトで下るころ、青空も見えてきましたが、山頂部は依然として雲の中でした。 下山後、温泉につかり、寒河江の木材屋さんに寄り冬の燃料、木質ペレットを購入、車いっぱい積んで帰りました。いよいよ冬の支度も始まりです。
青麻古道 アケラ山への道開通 2018年9月26日今日は古道の会の呼びかけに応じ、6人で作業しました。2人がルート探索、残り4人が刈り払い機という強力メンバー。 スタートは、白石牧場の三住登山口。ここからしばらく、車で行くことができます。標高650m地点の高萩山三角点近くまで車で、荷物を積んだ軽トラはさらに50mくらい先まで行けます。 そこから標高680mの遠刈田からの合流地点まで登りここから、刈り払い作業開始。約1㎞先のアケラ山までの道が今日の行程です。合流地点から640mまで緩やかな下り、そこから756m地点まで登り、そこから痩せ尾根を少し下り、標高823mのアケラ山まで、急登のガラガラ道の登り、そして笹薮の道を進みます。 登りは、ヤブコギでルート確定。そのあとを刈り払い機で道をつけます。10時過ぎ、先頭のルート偵察がアケラ山に到着。刈り払い機2人も11時前に到着。11時に戻り始め、下から刈り上がってきた2人と11時半合流。アケラ山までの道がすべてつながりました。 これで、横柴からのルート、北原尾からのルート、白石牧場からの2つのルートが、アケラ山、青麻山の登山道とつながり、青麻山西面の登山道が完成しました。 あとは、道標設置、一部ルートの刈り払い、など残りますが、青麻山を東からと西から登る横断ルートが完成しました。
2000mは紅葉の世界=西吾妻山を尋ねる 2018年9月23日連休の中日9月23日は天気が安定しているとのことで、日帰りで吾妻連峰の最高峰、西吾妻山を訪れることにしました。登山口、天元台は、意外なことに我が家から一般道で2時間の距離にあります。当初、吾妻連峰の東、一切経山に行こうと思っていたのですが、火山情報2になり、立ち入り規制されたため、吾妻連峰西のこの山を当たると行けそうなので、決めました。このルートは、楽なのでカミサンも行くことになりました。 この山(山頂)には、吾妻連峰縦走の途中でこれまで2度行っていますが、あまりいい印象がありません。というのも、吾妻連峰の最高峰にしては、山頂は周りの山林の中に、ただ柱が立っているだけ、ということだったからです。しかし、今回行ってみて、この印象はがらりと変わりました。 登山口からは、ロープウェーと3台のリフトを使って、標高1810mまで登ることができます(往復でJAF割引で3150円)。ロープウェーで登ると、そこは天元台の台地。北に飯豊連峰が見えています。こちらから見ると、飯豊本山と大日岳が並んで見えます。少し下って、リフト乗り場。3つのリフトを乗り継いでいきますが、乗降するたびにリフトが停止するので、あまり心地よくありません。最後のリフトの終点が、「北望台」。北側の米坂盆地と周りの山がよく見えます。蔵王は、米沢市街地の奥に見えます。 リフトを下りて、20分ほど登るとカモシカ展望台。石がごろごろして見晴らしの良いところです。そこを越えると、木道が出てきて、下り始めます。人形石への分岐を右に下ります。紅葉したミネカエデが緑の中に目立ち、大凹(オオクボ)の湿原が黄色く草紅葉になっています。100mほど下り、湿原の木道を進みます。 ここから、梵天岩まで130mほどの登り。登り口に、大凹の清水という湧水があります。とても冷たい。これを過ぎると、いよいよ急な岩だらけの道を登ります。ときには手を使う、いやな道です。登って平らになると、そこにはイロハ沼という湿原。そこからもう一息で梵天岩。360度の展望です(山頂の代わり?)。 ここで昼食をとり、なお進みます。すぐに吾妻神社のある天狗岩。平らな石だらけの広場です。ここもいい景色です。西吾妻山へは少し下り、水のたまった道を歩き、少し上ると、林に中に突然山頂の標識。周りは展望なし。そのまま進んで、若女平へ下る道に入り少し進むと、湿原の向こうに西吾妻避難小屋。ここにはトイレがあるそうです。 右に分岐する天狗岩に戻る道を進み、天狗岩へと周回コース。ここから来た道を戻ります。梵天岩、イロハ沼を過ぎ、急な岩だらけの道を下り、水場に出ると、ここからしばらく平らな木道。さらに80mほど登り返すと、人形石への分岐を経て、カモシカ展望台。20分ほど下り、リフトの駅に2時15分。3本乗り継ぎ、ロープウェイーで下りると、3時20分でした。そこから一般道を2時間少しで自宅に戻りました。 これまで2回の印象と違うのは時期。記憶によると、2回とも8月末か9月初めに行き、高山植物は終わるが紅葉には早い、緑の山の時期だったようです。ところが、今回、いろいろなものが色がついて存在を主張していました。紅葉したチングルマは、花の時期がどのようだったかを教えてくれます。前回は天気も良くなかった記憶があります。また当時、米沢は東京から遠く、2泊以上しないと行けない山だったのです。 ということで、今回は、西吾妻山の魅力を見直した山行でした。日帰りでも行けるというのがスゴイ。
三浦雄一郎氏講話 2018年9月18日蔵王町のございんホールで、三浦雄一郎氏の講話がありましたので、出かけてきました。 全国森林レクリエーション協会の青森支部・秋田支部合同研修会、ということで行われましたが、なぜ蔵王で?と疑問でした。町長の説明によると、蔵王町長が青森支部の代表で全国の副会長なのだそうです。それで蔵王町で行われるとのことでした。 三浦雄一郎氏は、プロのスキーヤーで、70歳、75歳、80歳でエベレストに登頂したことで知られていますが、その間の経過を聞くと、参考になることがたくさんありました。順風満帆ではなかったようですが、それを乗り越えてきたのは、意志の力だったようです。 いいお話でした。
アケラ山への道2 2018年9月18日アケラ山への道づくりの2回目です。 今日は、伐採地から上の作業道の刈り払いです。作業道は、10㎝くらいの竹の切株が続き、スパッツは破れる、長靴は穴が開く、という状態でしたので、刈り払って、歩ける道にしました。 秋の訪れを感じられるものとして、山椒の実、タマシロオニタケ、サワフタギの青い実、センダイトウヒレン(フボウトウヒレン?)などがありました。 北原尾に出て昼食。秋の空の下に南蔵王連峰や船形連峰、大東岳などがくっきり見えていました。
しばらくぶりの馬の背 2018年9月13日下から見ると、山の頭は雲の中ですがライブカメラによると、御釜が見えています。しばらく見てないので。馬の背稜線まで行ってきました。 途中、賽の磧と駒草平で工事をしています。どちらもトイレを作る工事です。不思議なのは、工事期間が平成30年8月1日~平成31年3月22日となっています。エコーラインは11月初めで閉鎖。当然工事もできません。あと1月余りしか期間がなくて、できるのでしょうか?また、完成の点検などは?謎ばかりです。 それはさておき、馬の背に行くと、シラタマノキやコケモモの実で、すっかり秋の風情です。お釜もしっかり見えていました。あまり人はいません。 森林管理署の方が、馬の背にある柱を修理していました。冬に天気が荒れるととても頼りになる柱です。 熊野岳の山頂にも人はいません。斎藤茂吉の歌碑がありますが、今日はそれを調べてみましょう。 「陸奥をふたわけざまに聳えたまふ 蔵王の山の雲の中にたつ」と書かれてある(らしい)のですが、なかなか読めない字もあります。 「を」を「乎」、「聳え」が読み取れません。「たま」も読めません。「の」は「乃」と書いています。「雲の」も「の」が読めません。「に」は「尓」、「つ」は「津」でしょうか? この碑ができたのは、昭和9年。そのころの漢文の素養のある人たちには読めたのでしょうが、流暢な行書の文字であることもあり、85年くらいたった今の時代にはスラスラ読める人は、稀有なのではないかと、見るたびに思います。 帰りに、不動尊のあたりの蔵王古道に倒木がある、という話でしたので、見てきました。2本の大きな木が倒れていました。7本切らなければなりません。けっこう大仕事になりそうです。
アケラ山への道 2018年9月11日蔵王町の真ん中にある青麻山は、町のどこからも見える「ふるさとの山」です。この山は、かつては、噴火して荒れる蔵王を祈祷で鎮める場であり(奈良平安の頃)その後は、修験道の蔵王での修行のスタート地点となった山でした。現在この山に登る登山道は、東側に2本しかありません。 この山に、西側からの道を作り、縦走できるようにしようという話が前からあり、いよいよ現実のものとなってきました。青麻山のすぐ西にある、アケラ山(こちらの方が数m高い)に登る道を北西側(遠刈田、北原尾)と南西側(白石牧場)からつけようという計画です。 すでにルートの選定は行われており、今日は、刈り払いに出かけました。一部林業で使った道もありますが、基本的には、昔の踏み跡などを利用して、新道作りです。 今日は、刈り払いの第1日目として、横柴ルートの一部と北原尾ルートの刈り払いと、白石ルートとの合流点の確認を済ませてきました。 あと2回は必要そうですが、完成すれば、青麻山の登山にいろいろなバリエーションができるようになります。この日は、距離5.5㎞、標高差250mの作業でした。
幻となった、大雪山の紅葉 2018年9月8日今年こそは、大雪山の紅葉を見ようと、準備していました。この時期に北海道に行くことは、仕事の関係上無理だったのです。夏の大雪山は何度も行き、高山植物のすばらしさに触れてきましたが、紅葉の時期は行けませんでした。 大人の休日切符がこの時期に発売になったので、8日から12日までで旭岳ロープウェーに行く計画を立てたのですが、まさかの大地震。函館までは行けますがその先はアウト。観光どころではない様子です。残念!! しかし、朝遠刈田の始発のバスで仙台に行けば、夕方には、旭川に着けるようになっています。新幹線の威力です。北海道は、近くなりました。
登山道整備 刈田峠~南屏風 2018年9月7日ガイド協会の登山道整備で、刈田峠から南屏風岳まで歩きました。今日の担当はチェーンソー。 前山の登りにあった、直径20cmくらいのハンノキを切断しました。これは、前々からみなさんが、頭をぶつけた、こぶができた、という登山道真ん中にある木です。 これまで、何度もジャマだジャマだと言われつつ、手鋸できるには太すぎで、延ばし延ばしになっていたのですが、今回チェーンソーを持ち込み切ることができました。 その後、縦走路を南屏風まで歩きました。太い木はなく、もっぱら手鋸で、道にはみ出した枝を払いました。 山は秋の始まりで、リンドウがたくさん咲いていました。また、ミネザクラも紅葉しはじまっていました。芝草平も草紅葉になり始め。チングルマはまだ紅葉していません。 時折、高曇りの空の下に、吾妻連峰や飯豊連峰も姿を見せました。水引平の池も稜線から見えていました。杉ヶ峰の頂上では、タカらしい鳥の姿も見えました。いよいよ秋の始まりです。
柴田町の里山歩き 2018年9月4日今日は、近隣の柴田町の里山歩きに行ってきました。 こちらの町では、11月3-4日に「全国フットパスの集い」というイベントを準備中だそうで、その準備の一環のイベントに参加ということです。歩いたコースは、「ゆずの里入間田コース」。 スタート地点は「柴田町農村環境改善センター」ここから6㎞余りの里山歩きです。9時にスタートしました。ガイドはこの地区にお住まいの方とのことです。このセンターには、青葉城にある伊達政宗騎馬像のレプリカがあります。この像の作者が、この地の出身の方なのだそうです。 センターを出て、しばらく行くと道標。石碑が建っています。地図も整備されていない時代の重要な情報源だと思われます。 次に訪ねた円龍寺はサルスベリの大きな木が迎えてくれました。こちらには、室町時代作の薬師如来立像と十二神将像があるということですが、御社の中でした。 一山超えた八雲神社は、たたずまいといい、参道といい、900年前に建立された歴史を感じさせられました。 「こだわり街道」では、昭和レトロの数々の展示物に驚きました。 雨乞(あまご)の大銀杏の木にもびっくりです。北限となる天然のゆずの木がたくさんあります。まだ青い実がなっていました。歩いて行ける範囲にこのようなびっくりがいくつもあるのでした。 五斗亀という名のため池でも、地元の方にいろいろと話していただき、興味が持てました。 終わりころに訪れた、奥野醸造という酢を作っている醸造所見学では、酢の製造過程を初めて見ました。 3時間の里山歩きでしたが、見どころたくさんの「宝の里」という感じでした。
第53回蔵王清掃登山 2018年9月2日宮城県観光課が毎年行っている行事、第53回蔵王清掃登山にガイド協会のメンバーとして参加してきました。 刈田岳レストハウスから、馬の背を通り熊野岳まで往復してごみを拾う、というイベントです。今年は、応募した一般参加の方16名、県、蔵王町、川崎町、仙台森林管理署の職員9名、ガイド協会6名で行われました。 山はすっかり秋で、馬の背を歩いていると、コケモモの実、リンドウ、アキノキリンソウ、シラタマノキ、そして、最後のコマクサなどが見られました。 拾ったごみを集めた後、刈田レストハウス周辺の外来植物の駆除、セイヨウタンポポを抜く作業を50分ほど行いました。さすがに30人もいると、きれいになりました。
このページのトップへ 前月の記事へ
(C)Akihiko URAKAWA
|