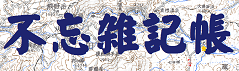澄川の紅葉・蔵王に初雪 2014年10月28日今日は、長老湖の湖畔巡りの予定でしたが、行ってみるとひどい雨。 予定を変更して、天気がまだ持っている、蔵王自然の家の奥にある、澄川に紅葉を見に行きました。 野鳥の森のコゲラコースを歩き、澄川の下降点に行くと、対岸には岸壁の上に見事な紅葉が見られます。 川まで降りて、見上げると、素晴らしい景色が・・・。ただ、天気が今ひとつなので、輝く紅葉は見られません。 それでも、黄色や赤の紅葉をしばし見物しました。 家から車で5分少し、歩いて1時間でこういう所もあります。 蔵王に雪が降りました。エコーラインは通行止めだそうな。遠刈田から見えるえぼしスキー場には、白い雪が見えました。いよいよ、冬の到来です。
栗駒山へ行ってきました。 山頂やイワカガミ平は、紅葉の盛りを過ぎていましたが、新幹線くりこま高原駅のそばのホテルに前日宿泊。6時に宿を出て、7時にイワカガミ平登山口。東栗駒山コースを登り、中央コースを下る計画です。 イワカガミ平の手前の九十九折りで、子熊が道路を横切り、藪の中に消えていきました。ここは、熊の生息地だ、と実感。写真は撮れませんでしたが・・・。イワカガミ平には、誰もいません。歩く準備をします。 時折強い風が吹き、雲海が広がっていますが、登山口を出て、高度を上げていきます。途中、栗駒山の山頂が見えていました。出発して1時間、新湯沢の沢づたいに100mほど登り、東栗駒山手前の岩に着く頃には、山頂と稜線は雲で覆われ、風に加えて、冷たい雨が降ってきました。寒冷前線が近づいている影響でしょうか。このまま進んでも、天候の回復は望めず、何も見えないので、ここで断念。引き返しました。 登山口に9時過ぎ。濡れた服を着替えて、下山です。ここの身障用トイレは、更衣室を兼ねていて、使わせて頂きました。更衣用のスノコがひかれたいました。 イワカガミ平を出て、高度を下げると、紅葉の真っ盛り。ここの紅葉は、大きな楓の木が多く、赤がとても鮮やかです。 帰りに、栗駒木材の工場に行き、燃料用の木質ペレットを360kg購入し、車に積んで自宅までのんびりドライブして帰りました。 やはり、栗駒山は、紅葉の名所です。来年は、時期を外さずに訪ねたいと思います。
ことりはうすの蔵王トレッキングで、青麻山に登りました。 山頂(799.2m)付近は、紅葉が進んでいます。下別当登山口からスタート。こちらからのコースは、急登の連続です。遠くは、薄雲がかかりぼんやりしているところもあります。 1時間半の登山でようやく着いた山頂付近の緩やかな坂では、ナラの木の紅葉が進んでいます。山頂からは、海までは見えませんでした。 神社の鳥居の前の広場で昼食。その後、電波塔コースへ下山。所々に鮮やかな赤の色が見えます。ウルシの仲間とハウチワカエデです。電波塔からは送電線の点検ルートで、下別当登山口へ戻りました。 高気圧に覆われた、秋らしい一日でした。
標高300m付近の我が家の周りでも、紅葉が進んでいます。 ヤマモミジの木も色づき始め、この春植えたブルーベリーの葉も赤くなりました。 近所を散歩すると、松川の中州はススキが見られ、土手の桜も色づいてきました。また、近所の別荘地の中でも、ドウダンツツジや桜が色づいています。 我が家の奥の林も、賑やかになってきました。
仙台で宮城県保険医協会主催の「公開市民講座」で「本当はどうなの?原発のコスト」というテーマで、講演会が行われたのに行ってみました。 大島堅一氏は立命館大学の経済学者。岩波新書「原発のコスト」の著者で、この本は2011年12月に初版が出たのを2013年第3刷を購入、読んだときに「衝撃」を受けた書籍でした。 福島原発事故以降、「原子力ムラ」という言葉が、普通に使われてき、一方、世の中には「原発は低価格のエネルギー源だ」という主張が流布されてきましたが、これを根底から吹き飛ばす中身を持った本でした。今流布されている「原発は安い」の宣伝のあやかしを暴く、まさに「目から鱗」の本でした。 この著者、大島堅一氏の講演が、仙台で行われることを耳にして、講演会に行きました。今回の講演、原発とそのコストの眼目は、「原発のコストは安いのか?」とともに、「誰がそのコストを払っているのか?」です。 原発のコストは、電力会社が、「安い!」と言っている原発運営のコストのほかに、多額の「社会的費用」から成っており。この費用は、福島の事故以降、保障や原状回復のためにどんどんふくらみ、他のエネルギーに比べ、高くなっている。 問題は、それを、国税や電力料金といった形で、電力会社ではなく、国でもなく、国民が払わされている、ということである、と述べられていた。いろいろな費用を電力料金に上乗せするように制度を変えてきたそうです。そういわれてみれば、電気料金の細目などは調べたこともありませんでした。 まさに、国民の目を欺き「再稼働しないと電気料金が上がる」と恫喝してきたこれまでの図が明らかにされました。「今、監視しないと、次々に電気料金に上乗せされ、国民負担になっていく」と言う指摘があった。 将来の見通し、の中で、原発の新設を許さなければ、次々と老朽化による廃炉になってていくという見通しは、原子力ムラにとっては悪夢であろが、原発0への確かな道が示されたように思えた。
紅葉が進んでいます。 昼間、エコーラインで、賽ノ磧まで登ってみました。ここでは、紅葉はそろそろおしまいの時期。 腹が白いホシガラスがせっせとハイマツを渡り、エサを食べていました。このあたりには、何羽もホシガラスがいます。木から木へと移り、開いた松ぼっくりの、奥の方にある、松の実を食べています。 紅葉は、今、澄川スノーパークのあたりから、不動尊、滝見台あたりが盛りです。高気圧に覆われた好天気のもとで、たくさんの車がエコーラインを上っていました。
野鳥の森の森林整備活動のお手伝いをしました。 林内には、枯れてしまった木もたくさんあります。そのままにしておくと、遊歩道に倒れてくる危険がある枯れ木を伐採する作業です。 遊歩道のそばにある大きな枯れた赤松を伐採します。チェーンソーで切り倒すのですが、周りに木がたくさんあるので、それを考慮しながら、倒す方向を定めなくてはなりません。 直径が50cmを越えるとなかなか大変です。それでも、チェーンソーという道具があるので、何とか切れますが、これがなかった時代には、斧で切るか大鋸で切るか、いずれにしても大変な作業だったと思います。
今日は、隣の村田町で行われた、「布袋まつり」に出かけました。 町は、おまつり気分が一杯。旗がかざられ、神輿と太鼓が練り歩き、獅子舞もいました。中央公民館前では、3台の山車が出番を待っていました。 村田は、蔵の町、みちのく宮城の小京都、というキャッチフレーズで売り出しています。江戸時代の蔵が並ぶ町並みが残っています。 午後1時20分、午後の部の山車の練り歩きスタート。七福神の仮装を先頭に、布袋を載せた山車が3台、大勢の人に引かれて町を回っています。 同時に、町にある白鳥神社のお祭りの日でもあるようで、神社の前は、出店が並び、境内に入ると、蛇藤と呼ばれる大きな藤や、直径が2m以上もあるケヤキ、イチョウの大木がありました。 道の駅にある、村田町歴史みらい館には、伝統芸能や村田の歴史が展示されていました。
秋晴れが続いています。今日は、蔵王町の南にある七ガ宿町を訪ねました。 途中にある、白石市の「どうだんの森」をそろそろ紅葉の季節かなと、見に行きました。途中から見上げる南蔵王の山々は、朝の日を浴びて紅葉しているのが見てとれます。 どうだんの森へ行ってみると、一部のドウダンツツジは、紅葉していますが、全体としては、今ひとつでした。 そこから、七ヶ宿ダムで作られた、七ヶ宿湖のほとりにある道の駅へ。行ってみると、様子が少し変わっています。湖の際にあったのですが、この4月に、七ヶ宿公園内に移転したようです。昼食を取って、隣にある「水と歴史の館」を見ました。町立博物館、と言った位置づけで、縄文時代の遺跡の出土品、江戸時代の出羽街道時代の展示、特別展示室では、「出羽13大名が通った街道(みち)」〜七ヶ宿街道・参勤交代行軍録〜という企画展がありました。また、ダム湖に沈んだ3つの集落の記録などが展示されています。 そこから、ダムの堰堤に行くと、ちょうど、大噴水の打ち上げの時間で、遠く不忘山の見える湖面から高く上がっていました。管理所1階には資料室があり、ダムカードも頂いてきました。 さらに、その下流にある「材木岩公園」へ。ここは、安山岩の柱状節理が見られるところで、高さ65m幅100mの壁には驚かされます。また、七ヶ宿街道上戸沢宿にあった旧木村家住宅を移築した、検断屋敷という旧家があります。 秋晴れの一日、ドライブがてら訪ねた七ヶ宿町でした。
秋晴れが続いています。今日は、昨日見た屏風岳からの紅葉と芝草平の様子を見に行きました。 刈田峠の駐車場は、平日なのに結構埋まっています。9時半スタート。ススキが出て、秋らしい景色です。 登山道の入口には、「除草中 登山道」の標識が。進んでいくと、宮城蔵王ガイド協会の方々が、登山道の刈り払いをして下さっています。 芝草平は、草紅葉を過ぎて、冬の始まりの風情です。野イチゴの実がありました。葉は枯れています。ナナカマドも、葉を落として、実が鮮やか。これくらいの標高では、紅葉は終わり、冬の準備中、と言ったところ。 屏風岳に登り、「宮城県最高地点」には、「地理院地図」では、1825mの標高点が書かれていますが、2台持っていったGPSでは、1830mを越えています。Garminでは1831m、iPhoneでは1833mです。 屏風岳三角点付近から、西側の烏帽子岳、水引入道の間に見えるのは、秋山沢の上流ですが、見事な紅葉です。 昨日は、後烏帽子の右に見える、前烏帽子からの紅葉でしたが、こちらから秋山沢を見下ろすと、烏帽子から水引入道まで紅葉が広がっています。 帰りに、芝草平を通るときに、おびただしい数の小鳥の群れが北から南へ飛んでいきました。一瞬のことで、何という鳥かわかりませんが、南へ渡りを始めているようです。 山形側の山腹も、色鮮やかな紅葉が見えました。秋も盛り、少しずつ、季節は冬へ移っていきます。
台風一過、秋晴れのいい天気になっています。今日は、午後に用事があるので、午前中、前烏帽子岳に登りました。 自宅を7時に出発。えぼしスキー場の少し手前に、道路のカーブした地点に駐車場があり、ここが登山口。道路脇の道標から入ります。 途中、小阿寺沢を飛び石伝いに越え、ひたすら登っていきます。 はじめはブナを中心とした林ですが、紅葉はまだです。高度を上げていくと、左右の木々が色づいています。登り始めて2時間半で、前烏帽子の山頂。地形図とはルートがだいぶ違います。三角点は通過しません。 山頂の看板の後には、大きな岩がごろごろ。それに登ってみると、一挙に展望が開けます。紅葉した後烏帽子岳、北屏風岳から南に続く稜線、馬ノ神山、反対側には、紅葉した木の奥に、人家が見えています。山頂あたりは、紅葉の真っ盛り。 山頂で、しばしの休憩の後、下山開始。途中、色づいた雁戸山なども見えています。麓のブナ林に入ると、もうすぐ登山口。7時半に登り始め、12時に下山しました。 夜は、皆既月食。少し写真を撮りましたが、輝かない満月の周りには、星がいくつも見えていました。
10月4日・5日と、遠刈田の宮城蔵王こけし館で、「第26回全国伝統こけしろくろまつり」が行われていましたので、行ってきました。こけし館の開設30周年だそうです。 いつもと違い、こけし館前には、ずらりとテントが並び、向かって右側のテントには、東北地方のこけしの11系統の工人さんが店を出し、いくつかの所では、こけし作りの実演をしていました。反対側のテントには、くじ引き、いろいろな売店、食べ物販売等並び賑やかです。こけし館は無料で開放されました。 館内では、フランス人の一行が、こけしの絵付けに挑戦中でした。 また、蔵王町の保育園児の塗り絵や、全ての小学4年生の絵付けしたこけしが展示され、優秀作品には賞が与えられていました。 宮城県全町村の花や物産にゆかりあるこけしが「花咲きこけし71」と言うタイトルで展示されていました。また、珍しい、インディゴ色のこけしもありました。 外のテントでは、昼時に、「芋煮」が無料でたっぷりと振る舞われました。 この機会に、なかなか手に入らない、南部系の煤孫盛造工人と木地山系の北山賢一工人 のこけしを購入し、我が家のささやかなコレクションに加えました。
このページのトップへ 前月の記事へ
(C)Akihiko URAKAWA
|